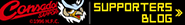2008年02月29日
aftertalk #25
clasics #25でした。 そして、今回のaftertalkはもう時効になった今だから話せる、重い話です。 この札幌に帰った時、というのは7月の中頃から下旬くらいのことだったと思う。仕事でさんざん疲れて精神的に参っているという話はさんざんここでしてきたけど、ついにそれが決定的な形となって現れたので休職して一週間ほど実家に帰っていたのだ。現状報告と、頭を下げに。 その決定的な形というのはいつもと変わらない、たいして眠れなかったまま朝を迎えたある日のことだった。いつもどおりにシャワーを浴びて目を覚まし、いつもどおりに電車に乗った。MDのボリュームを迷惑にならないギリギリまで上げて、ただ音楽に集中していた。仕事の事なんて考えたくなかったし、職場にいる先輩や上司のことはもっと考えたくなかった。でも、奥歯を噛み締めながら乗り換え駅の大岡山に着いたとき、それが爆発した。 目の前が真っ白になって、足はがくがくと震えだし、立っているのも辛くなってベンチにへたり込んだ。全力疾走を止められないかのように息は苦しく、呼吸を上手く行うこともままならない。 ここはどこなのか、ここにこうして立っているのは誰なのか、 果たしてそれはほんとうに僕自身なのか、 このまま死ぬのではないか、ひょっとしたらこのまま死んだ方が楽なのでは、 いや、 まさか、 ほんとうに、 どこかが壊れてしまったのか―― 30分もするとその症状は治まり、ともあれ僕は汗びっしょりになりながら会社に行った。とりあえず最低限の仕事をして定時には帰ることにした。その間、いつあの朝に起きた発作のようなものが再発するのではないか、再発したらどうしよう、こんどこそ狂ってしまうのではないのか、なにかひどい病気だったらどうしよう、そんなことばかりを考え続けて、身体に始終弱い電流を流されているような震えを止められず、翌日に近くの大学病院に行くことにして、電車の中でもびくびくとおびえ、身を縮め、乗り換えの駅になるたびにベンチで休みながら家まで帰った。 この僕の症状はなんなのだろう。明日病院に行くにしても、どんな病気なのかの見当くらいつけておかないと心配だ。ましてや、いちばん近くの大学病院って言ったってバスにゆられて30分はかかる山の中だ。何も知らずにまた今朝のような突然の不安の渦に巻き込まれるようなことは避けたい。 とりあえず今朝自分がうけた症状から病名を検索してみた。 1,自律神経失調症 2,パニック障害 ああ。あああ。 とうとう、病んでしまったのか。 僕がいちばんなりたくなかった「弱い人間」に、なってしまったのか。 なんて格好悪い、なんて悲しい、なんて情けない、なんて恥ずかしい。 なんて、死にたいくらいに。 結局、その日も眠れぬ夜を過ごしたまま、キレイに青い夏空に輝く太陽が昇った。 やっぱり病院に行くまでの道中は怖かった。僕がこんな病気だと診断を下される事が怖かった。会社での反応と、僕に投げかけられるであろう蔑みと諦めの視線が怖かった。そして、もう札幌の応援ができなくなるんじゃないか、というのが、何よりも怖かった。 アンケートに症状を記入し、薄暗い病院の奥まった診療科で待つこと2時間。医師は初診の僕にあっさりと「パニック障害ですね」の一言を告げた。それを言われたときはなぜか気が楽になったのを覚えている。ああ、何はともあれ病気だったんだ、と。診断書を書いてもらって、薬を出してもらって(そしてその薬の高さにびっくりして)、とりあえず家に帰って薬を飲んで寝た。 今まで眠れなかったのが不思議なくらい、よく眠れた。 その翌日何とか出社した僕は、課長と部長を小さな人目につきにくいミーティングスペースに呼び、診断書を出した。2人とも部下からこういうメンタル系の病気になってしまった人間を出したのは初めてのようで、ただただ困惑していた。休養が必要ということだからということでとりあえず有給で2週間休むことがあわてて認められ、僕は実家に事情を話し、残っていた仕事を放棄して翌日には札幌へ帰る飛行機に乗っていた。とにかく一刻も早くこことは違う場所へ行って、気持ちを落ち着かせたかった。そしてそれができる場所は、僕には、実家しかなかった。千歳から列車に乗り、地下鉄に乗り、バスに乗り、そして歩いてきた僕は家のドアの前に立ち止まった。 なんて、なんてことになってしまったんだ――。 気づけば、自分は立ちつくしたまま玄関でぽろぽろと涙を流していた。涙は一向に止まらなかった。今の方向からは賑やかなテレビの声と、両親の会話が聞こえる。今から自分は、あの両親のささやかだけど幸せな生活をぶちこわしてしまうのかもしれない。自慢の息子が心を壊して帰ってきたなんてかっこ悪い喜劇のような悲劇で。でも、ここにしか身を寄せる場所もない。申し訳ない、ごめんなさい、そう思いながら、何かにすがるように、インターホンを押した。泣きながら、僕は、いきさつを話し、診断書を見せ、夕食も取らずに部屋に閉じこもってただ眠った。 何日かが過ぎて、突然に父が外で晩ご飯を食べよう、と言い出した。 家の近くに、イタリア料理店ができたのだそうだ。それが前回で出てきたお店のことだ。食事の間両親は特になにも僕には言わなかった。言わない方がいい、と気を遣ってくれたのだろう。僕にはその気持ちが本当にありがたかったし、本当に申し訳なかった。言ったとしても、それは「無理するな」「無理だと思ったらいつでも帰っておいで」というくらいの言葉だった。僕はそのとき東京に骨を埋める覚悟だったから、両親には申し訳ないけどそうならなければいいな、と思った。白身魚のソテーと白ワインとパスタが、ほんのちょっとだけ僕の心を緩めてくれた。とりあえず1週間ここで生きられると思った僕は、少しだけのワインでかなり酔ってしまった。 何も言うまい、余計な口出しはすまい、と両親は僕が帰ってくる前に決めていたのだろう。実家にいた間、病気のことを僕に細かく説明させようとしたり、生活態度が多少乱れても怒らなかった。いつも通りに、盆や正月に帰ってきた時のように、普通に接してくれた。それが僕にはありがたかったし、申し訳なかったし、余計なお世話だという気持ちも少しあった。素直にありがとうと言えなかった。僕は両親のその気持ちに気づこうともしなかった、というか、自分がこの先どうなるのかという事ばかりをずっと考えていたから、他のことを考える余裕がなかった、というほうが正しいかもしれない。でも、あの時のことを思い出していちばんに思うのは、両親への感謝と、自分の情けなさだ。 また東京に戻ったら原稿を書こう。がらっと文体を変えて、開き直って吹っ切れた、さっぱりした文章を書こう。ですます調をやめて、きっぱりと、淡々と。そう思って、僕は残りの1週間を会社復帰へのリハビリに充てるために、東京へと戻った。 そしてこの病気が、僕がコールリーダーを辞めた最大の理由。
posted by retreat |00:48 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(0)