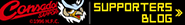2008年04月28日
aftertalk #44
clasics #44でした。文脈のそこかしこに、当時影響を受けまくりだった村上春樹と西尾維新っぽい表現がある。そういやこないだ西尾維新のデビュー作「クビキリサイクル」が文庫化されてたので、ついつい買ってしまったんですけどね。この作品読んだときは、けっこう衝撃的だった。こういうこと考えて書いてもいいんだ、と。村上春樹をはじめて読んだときのことを思い出してもそうだけど、自分が本を読んで衝撃を受けるときって「こういうこと考えててもいいんだ!書いてもいいんだ!」っていうことで衝撃を受けることがほとんどだ。それはつまり自分の頭の中が良からぬ妄想満載だけども言葉にできるほどのスキルがない、ということとと、「俺はヘンじゃなかった」とどこかを許されたような気持ちになるということ。つまり自分は本を一冊読むたびに「これでいいんだ!」と心のリミッターをひとつひとつ外していることになる(外れないときもあるけど)。でも20年以上本を読み続けてきて、いまだに外れないリミッターがあるっていうのも自分の心のひねくれて頑ななところを感じさせてがっかりする。自分で自分に。 そしてJリーグ開幕に遭遇し、コンサドーレを知った自分は、どれだけ読んでも読み終わらないサッカーの奥の深さを思い知ることになる。リプレイをどれだけ見ても、生で試合をいくつ見ても、実際に自分でボールを転がしてみてもわからないことが多すぎる。多すぎるからこそ面白い。文章を読むだけでは体験することのできない論理と、システムと、神様のいたずらとしかいいようのないちょっとの運がそこにある。サッカーだけではない。バスケットでも、スキージャンプでも、野球でも、カーリングでも、そこにはスポーツを通してしか味わうことのできないロジックとドラマが隠れている。すべてが掌の上では転がしきれないシーンが溢れている。本ばかり読んでいて他のことには余り興味がなかった自分がスポーツを見るようになったのは、そういうところに惹かれたからかもしれない。自分でも剣道と弓道をやっていたけど、どっちかというとそれらからはプレーよりメンタル的なところで多くを教わった。剣道に関していえば才能は弟のほうが格段に上だったし、部活や道場でも下から数えたほうが早いような実力だった。試合に出ても3回戦まで勝ち進めればOK、みたいな。だから剣道の「精神」とか「心」とか、そういうほうに興味が傾いた。上には上がいるという絶望感と、自分に無い才能を持っていることへの嫉妬、はがゆさ、そういうのはスポーツから学んだけど、チームプレーのロジックを最初に学んだのはサッカーからだった。チームで戦うということ、勝つということの楽しさを学んだのも。そんなことを思いながら、今でも月に10冊は本を読んでいる。
posted by retreat |18:33 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月27日
CONSAISM clasics #44
clasics #44、なんか斜めに構えているっていうか何というか、な回。
J2のリーグ戦が半分終わった7月の初めから半ばの中断期間。J1ではここ数年よりはずっと面白い(少なくとも鹿島か磐田かの二択ではないので)優勝争いが繰り広げられていて、試合がBSで放送されているものであれば片っ端から観ていた。鹿島と磐田のいわゆる「2強」がそれぞれにどこか不安定な戦い振りを見せていることもこの混戦のひとつの要因だろうけど、オシム監督のもとに鍛えられた市原の試合がとにかく面白い。走って走って走って奪って奪って奪ってスペースに走る。村井が坂本が阿部がクロスをどんどんと上げてそれをまたチェ・ヨンスがばしばしと決めていく。一見したら体育会系なシンプルさだけど、そこに元から市原に見られた技術の高さが組み合わさってそれがまた相乗効果を産んで、どこか学者然として何をしでかすかわからないようなオシム監督の表情と相まって僕のフットボール的好奇心を膨らませる。ちなみにこの原稿を書いているのは磐田対市原戦の直後、チェ・ヨンスがヴァンズワムをあざ笑うかのようにふわっと浮かせたPKの余韻がまだありありと残っているぐらいの時間だ。タフで締まったいい試合だった、と思う。 さて、そうすると札幌の試合がなかったこの2週間ほど僕は何をしていたのかというと、相変わらず本を読んでばかりいた。なにしろ自分自身で憶えている最初の自分が「畳の上に寝転がって絵本を読む自分(当時2歳)」くらいなので、ほぼ生まれた頃からずっとなにかの文字を読むことに時間をかけてきて、例え財産が無くても本にかけるお金には糸目はつけないというのがもう自分の中でひとつのルールにされてしまっている。どうしても糸目どころか糸くずも見つからないときは父の書棚をひっくり返してよくわからないながらも何か文字を目で追い、それでもなければ新聞を隅から隅まで、それこそ株価の欄に至るまで読むような子供だった。今思い返すと嫌な子供だとつくづく思う。 どうしてそこまで本を読むこと(文字を読むこと)が好きだったのかというと、文字というひとつの定まったスタイルから拾い上げた情報だけを使って、そこにある情景や物語、あるいは100年も1000年も先の世界、そして今いるこの世界とは全く異なる別の世界を想像することができたからだった。知らない言葉は調べて覚えて、文章の使いまわしに感嘆したり難渋したりしながら読み進め、そこからしだいしだいに浮かび上がってくる世界やその世界を作り上げた作者の掌まで想像し、僕の頭の中に創造されていくのがとても好きだった。そうやって本を読み続けて20年以上、たまった知識は多いだろうけれどもほとんどは今テレビでやってるアレ、「トリビア」だったりもする。でもまあそれでも楽しいからいいんだけど。ちなみに僕はあんまりマンガは読まない。なぜかというとそこには言葉以外に「絵」というものがあるので、それが存在することによって僕自身の創造できる「世界」がどうしてもその絵に規定されてしまうからだ。それでも読むマンガがあったならば、それは僕がものすごく好きな絵を描く人であったり、マンガでしかできない表現があったりするからだったりする。しかしこうして本ばかり読んできたせいで、僕はその世界に結構引きずり込まれてしまってリアルの世界ではなかなか人付き合いが苦手だったりとっつきにくいやつだと思われているようで僕自身もそれを痛感している。とりあえず思ったことをきちんと相手の顔を見て伝えるということはとても大事だとしきりに思うこのごろ。 じゃあ自分はただの本オタクで引きこもりがちなヤツなのかと言われればまあ否定はできないのだけれども、本を読むということで国語の成績はよかったということ以外にとりあえず身に付いたのは「ものごとを読み取ろうとすること」だ。ある文章を読んでそこにある風景や心情や作者のほんとうに言いたいことを読み取ろうとその文章の中にある世界を類推し、理解しようとする。そのことをずっと意識していたおかげでリアルの世界においてもそういう力(というか癖、なのかも)がついた。文章でなくても、目の前の出来事でも人の発したひと言であってもそういうことをまず第一に考える。その物事が行われている背景には、必ずそうせざるを得ない「状況」や「理由」があると思うからだ。例えそれが「なんとなく」という理由であっても、言い換えてしまえば「本能」といってしまうこともできるし、そういう「本能」が生まれた要因というのは必ず存在すると思って今まで僕はそうやって物事を考えてきた。そしてフットボールもやっぱりそういう風に観るようになっていた。例えば左サイドのスペースに出された一本のパスにしたって、そこにスペースが生まれたのは中央なり右サイドなりで相手の注意をひきつける動きがあったからこそだし、そこにパスが出されたのは味方がそのスペースに動いていってパスを受けチャンスを作り出す動きを戦術的なものとして叩き込まれているから、はたまたさっきの「本能」的なものであれ予測されてのものであって(「苦しまぎれ」という理由もたまにある)、そこにボールが出てフィールドでどういう変化が起こるのか、つまりゴールを生み出すためにどうするべきなのかというのをプレイヤーも監督も考えているからこそのパス一本、トラップひとつなのであって、やはり僕が考えて行き着くところは「フットボールというのはかくも考えさせられるスポーツなのか」ということなのだ。そうして味方のことを考え、自分のことを考え、敵のことを考え、その結果行き着いたボールの流れを見てまた僕はそれぞれのことを考える。そのボールの行き着く先と、そのボールの交差によってフィールドに描き出される世界を。そうして絶対にどう考えてもだれに聞いても「わからない」という答えしかでないプレーやゴールを見ることがある。そこがまた僕の好奇心を刺激して、また深くフットボールにのめりこんでいく。答えの出ないミステリを読んでいるような、結果があって理由をどうしても導き出せない戯言だらけの推理小説のような、そんなところが面白いのだと思う。このフットボールというものはまだまだ僕なんかの想像力が及びもつかないところがいっぱいあるし、多分その量は増えこそすれ減らないだろう。どうやらこの「フットボール」という名の本はまだまだ読み終われそうにない。
posted by retreat |22:16 | classics | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年04月26日
aftertalk #43
CONSAISM clasics #43でした。この話をしても、いまだに誰も信じてくれないのがちょっと寂しい。ホントだったんだってば! 札幌に帰ってからも歩くのは好きだった。大学時代に川沿いを歩いてよく帰っていたときから、東京の街と海辺を歩き、遠征で歩き、そして札幌に帰ってきたときは必ず札幌駅から大通駅まで歩いて(もしくはその逆)町並みというかテナントの入れ替わりを見ながら歩くのが恒例だった。今では仕事の帰りに地下鉄一駅ぶん歩いたり、休みのときはぶらっと散歩したりしている。散歩ってのは頭が空っぽになるので良い。仕事でオーバーヒートした頭も、少し歩くことで冷却されて寝付きが良くなったりするので。そうやってぶらっと歩いていた時に遭遇したのをこの回では書いている。 イバンチェビッチは札幌をサルベージできないまま、わずかな期間で去ってしまったということもあって余り評価のされていない監督なんだけど、個人的には好きな監督だったし、それなりの評価をしたいと思う。あれだけボロボロにされたチームを戦術的に整備して、ある程度の目処をつけて戦えるところまで戻したというのは「できるだけのことはやった」という個人的な意見を出したい。あれ以上のことをやるにはクラブ自体の体力も足りなかったところがある。もちろん、それで「降格して当然」みたいな考え方なんてのはなかった。与えられた条件と、選手と、ファンが一体になって乗り越えるべき、地方の小さなクラブの壁なんだと思ってわくわくしていたくらいだ。夏のアウェー神戸で「イバンチェ!イバンチェ!」とコールをしたら、ベンチに座っていたイバンチェビッチが飛び出してきて、僕らの陣取るゴール裏に向けてぶんぶんと手を振ってくれた。それだけでものすごく親近感がわいてきて、この監督と一緒に戦うんだ!という意識がものすごく強くなった。ベストメンバーを組んで、そこからいけるところまで行く、という戦術も納得できたし、それによって控えに能力のある選手がいなくなるというのもわかってはいた。それでもイバンチェビッチのやり方について行こうと腹をくくっていたんだけど、それ以上に強化しなければいけない部分(主に戦力の獲得的な部分で)の壁があまりにも高くて成し遂げることはできなかった、そのうえでの「No idea.」という発言だったのだろうと思っている。 でもあのときの光景ははっきりと今でも覚えている。外に面したカウンター席で、コーチのボージョビッチとともになにごとか熱く語っていたのを。それを歩道から、僕は見ていた。思わず駈け寄り、こう伝えたかった。「あなたを信じている」と。「大丈夫だ、僕はあなたを応援している」と。 イバンチェビッチは今、セルビアリーグ1部の「FK Smederevo」の監督を務めている。彼が日本のことを思い出すとき、どんな感情を持って思い出すのだろうか。
posted by retreat |00:31 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月24日
CONSAISM clasics #43
clasics #43です。「夏と私とイバンチェビッチ」というタイトルとともに、個人的にはかなり好きな文章のひとつ。
JR札幌駅から大通公園へと続く道をそぞろ歩くのがなぜか好きで、晴れの日も雪の日もこの道を歩いている。札幌を離れてから、お盆や正月に帰省してきたときはまずこの道を大通公園までのんびりと歩いて札幌の空気を吸い込むのがひとつの儀礼のようになっていて、夏なら大通公園で青空に噴水の湧き上がる様に涼みながら往来をぼんやりと眺めるも良し、また冬なら冬で雪と寒風で冷えた身体を喫茶店で温かいカフェラテでも飲みながらこれまたぼんやりするも良し。そうしてこの癖は札幌に戻ってきた今も変わらずにいる。 この間も同じ道を歩いていた。そのときは札幌駅を背にして右側、道庁に近いほうの道を選んで歩いていて、札幌第一ホテルの脇を通り過ぎるときにはその1階に出店しているスターバックスが視界に入る。ちょうどガラス張りのカウンターの部分がちょっとだけ歩道にせり出していて、店の中からの視線は歩く僕らを回遊水槽の中の魚達でも眺めるかのよう感じてしまう。いつもならそんな光景には慣れたので歩いていってしまうのだが、一年前のある日に、僕はそこにある二人の人物の姿を認めて、立ち止まらずにはいられなかった。当時札幌の監督であったラドミロ・イバンチェビッチと、同じくコーチであったミオドュラグ・ボージョビッチだった。 柱谷哲二元監督の更迭によって札幌にやってきた、東欧のブラジルと呼ばれた、ユーゴスラビア(現セルビア・モンテネグロ)よりの救世主。僕はこの人の名前を寡聞にして知らず、戸惑いながらもその経歴とメディアの大きな報道を見て、とりあえず諸手を上げて歓迎してみた。そして二人を始めて見たのは6月の御殿場合宿のとき。グラウンドにはまずボージョビッチが姿を見せた。時を同じくして加入したFW、バーヤックとともにゆっくりとグラウンドの外周をランニングし始める。しきりに彼はバーヤックに話し掛けていて、それは初めて日本に来たまだ若い彼の緊張を早くほぐしてやろうという風に見えた。そして理知的で紳士的に見える彼の姿、でもその底には計り知れないフットボールへの静かな情熱があるだろうということも感じたような気がした。 全体練習が本格的に始まる頃、イバンチェビッチ新監督がやってきた。ジャージを着たその体躯はぱっとみたところ「フツーのオジサン」というような感じで、このひとが本当に札幌を変えるんだろうかといった第一印象だった。ハンチング帽に新聞と濃い目のコーヒーを添えてベオグラードの街角に置いたらそのまま風景に溶け込んでどこにいるのかもわからないような、「フツーのオジサン」的な風貌。まあ実際には僕はベオグラードには行った事は無いのだが。ともあれ、僕にとってそれがイバンチェビッチとボージョビッチとの最初の邂逅だった。 ワールドカップが終わり、Jリーグが再開に向かっていく中、札幌も力をつけているように思えた。選手のコメントからは充実感があったし、マスコミの記事もこの実直な新監督の指揮を好意的に捉えていた。そんな中で僕は、7月初めの1週間ほどを実家で過ごすことになった。自分の中のどこかで無理がたたったのか体調が悪化し、2週間の静養を医者から言い渡され、とりあえず半分を実家で過ごすことにしたのだ。まだ夏の盛りにはちょっと遠い午後の日に、いつものように僕は札幌駅から大通へとあてども無く歩いていた。風は爽やかだったけど、僕の心はこれからの焦りと不安と疲れで淀みっぱなしだった。その途中で、僕は二人の姿を見たのだ。そのスターバックスの、ガラス張りのカウンターの向こう側に。回遊水槽を眺められる向こう側から見たら、そんな僕の姿はさぞかし生きの悪い目の濁った魚に見えたに違いないだろう。でも二人はそんな僕や他に過ぎ行く人々には目もくれず、何かを話していた。白に緑のアクセントがついた紙コップを前に、イバンチェビッチが熱心に手ぶりを交えながら話している。ボージョビッチがそれを冷静に聞いている。その光景がしばらく続いていて、僕はそれを見過ごして歩くことが出来ずに二人を見つめていた。それのほんの数秒間だったのだろうが、なぜか僕はとても長い間彼らを見ていたような気がして、突然にそんなことをしていた自分が下卑た感じがしてなんだか恥ずかしくなって、ちょっとだけ早足でまた歩き出した。 あの時の彼らはとても、とても、熱を発しているように見えた。札幌をどうにか立て直していこうとしている、彼らはそれを成し遂げられると信じているのだ、と思った。こんなことを、あんな熱を、これほど身近に感じたのは初めてだった。 あの時二人は何を話していたのだろうとふと思う。戦術なのか、戦略なのか、それともそれすらを超えたフットボールの哲学とも言えるような話だろうか。あれからおよそ一年が経って、彼の思いが聞きたいと何故か僕は思っている。そうして僕はこう言いたいのだ、確かに結果は伴わなかったが、あなたが札幌で成したことは間違っていなかったと。少なくとも僕はそう信じているのだと。もう一度会う機会があったら、僕はそう言いたい。そして僕はあなたの姿に励まされたのだ、と彼に感謝したい。そんなことを思い出しながら、なんでもないのに勝手に一人で少し恥ずかしく思いながら、僕はあの時イバンチェビッチの座っていた場所で、揺れ動く回遊水槽を眺めている。今年は去年より暑い夏になって欲しい、その熱がずっと続いて欲しいと思いながら。
posted by retreat |22:37 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月22日
aftertalk #42
clasics #42というわけでした。 ここでは割愛してるけど、毎回このコラムにはタイトルをつけていて書き上がってもどんなタイトルにすればいいのか、と結構悩んだこともあった。その逆に、タイトルだけがぱっと浮かんできてそのまま書いていくということもあった。どっちかというと、タイトルが先に浮かんだほうが書きやすかった。ちなみにこの回のタイトルは「変わり続けるシーン」で、小沢健二の楽曲からもってきた。タイトルがどうしても思いつかないときはこうやって音楽とか他の小説などからもってくることが大半で、それでもなければシンプルに一言の言葉で。そうやって何かから持ってきたタイトルのほうが文章にしっくりきたりすることが多かったのは地味にがっかりしている。キャッチコピー的なものを想像する自分の能力のなさに。その際たるものが次回分のタイトルで、「夏と私とイバンチェビッチ」という。こっちは乙一の小説「夏と花火と私の死体」からそのまんま持ってきたら、意外と内容とぴったりきてしまった。人を引きつけるようなキャッチコピーとかタイトルというのは難しいものだ。 これを書いていたときはちょうど実家に戻ってふらふらしていたころで、宮の沢にもよく通っていた。天気の良い、からりと晴れた日にのんびりと練習を見るのはとてものんびりできて、サテライトリーグの試合でものんびりじっくりとサッカーを見ることができた。肩肘を張らずに過ごせる貴重な時間は、大学を出てからの2年間でいいかげん疲れ果ててしまった自分にとっては何ものにも代え難いものだった。そしてこのころにはサテライトだけじゃなくてプリンスリーグも始まり、北海道でもサッカーを見る機会が増えたのも嬉しかった。昔はサッカーを見ると言うとコンサドーレ以外だったら道リーグか天皇杯予選、ちょっと新しめのところだと夏の国際ユースサッカーくらいしかなかったので、まるまる一ヶ月生のサッカーを見ることはなく過ごすというのはなくなった。そういうところで、北海道のサッカー事情というか、スポーツ全般において北海道は「後進国」ではなくなっているのかなあとも思う。天気の良い日に外で見るサッカーというのは、本当に気持ちいい。
posted by retreat |20:55 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月21日
CONSAISM clasics #42
clasics #42です。札幌に帰ってきて思ったこと雑感、てな感じ。
リーグの開幕から約3ヶ月弱、よくもまあいろいろなことがあったものだと反芻する。 開幕でのまさかの敗戦から守備は崩壊攻撃は決定力不足を露呈、ジョアン・カルロスの外科手術(荒療治とも言う)で守備陣は安定してきたものの怪我による戦線離脱は重症軽症後を絶たず、頼みの綱の外国人はベットがいきなりブラジルに里帰り、とどめにご存知の通りウィルのアクシデント。これだけ短い期間でこれだけマイナス要因がぞろぞろと出てくるのは未だかつて無いんじゃないだろうかと思うくらい。それでも5月はどうにかこうにか無敗で乗り切っている。残念ながらそれも6月の早々に途切れてしまったけれども。 今年はJ2のリーグ戦以外にもいろいろなことが春の訪れとともに新しくスタートを切っていて、こっちは喜ばしくもプラス要因。ひとつは北海道U-18プリンスリーグ。道内で選ばれた8チームがリーグ戦を戦いながら、北海道の高校生世代のサッカーシーンの底上げを図るために発足された。そしてこのリーグに参戦しているひとつがコンサドーレ札幌ユース。2節を終了して、1勝1分けとまずまずのスタートを切っている。この時期に北海道の学校のサッカー部、あるいはクラブチームが集まってひとつの大きな試合を行うということは今までになかったはずで、どのチームも試合運びがうまくいかなかったり、連携が取れないことが多かったりする。戦術自体も守備から入るチームが多く、まだまだこれから、という感じがする。これが夏になり、初秋になり、クラブユース選手権や冬の高校選手権をだんだんと視界に大きく捕らえていくにつれて、どのチームもそれぞれのチームの色が出た成熟したプレーを見せてくれるだろう、と勝手に期待して思っている。 そしてもうひとつ新しく始まったのがサテライトリーグ。宮の沢でのホームの開幕戦には2300人を超えるファンが詰めかけ、そして東京V戦ではリーグ初勝利をものにした。宮の沢の雰囲気は厚別やドームでのトップリーグとはまた違うもので、あまり肩肘張らずに楽しもうという感じである。そんな雰囲気の中である選手はトップでの出場を狙いアピールし、ある選手はルーキーとしてプロの世界の当たりの強さや手ごわさを次第に身に付けより逞しくなろうとし、またある選手は怪我からの回復を確かめ、試合勘を取り戻しつつある。そしてサテライトリーグの参加の意義のひとつとして「若手育成」を掲げるこのチームにおいて、ユースからも将来を担うであろう幾人もの選手がすでにそのピッチに立っている。そんな光景を、多くのファンがスタンドで温かく見守り、声援を送っている。いいプレーには拍手を、悪いプレーには「次だ、次!」と励ます声が挙がる。それは厚別やドームとはまた違う、ある意味殺伐とした「戦い」よりも、未来の萌芽を育てていこうとする「成長」を楽しみにして見守っていこうという雰囲気。そして宮の沢はピッチが近く、「生」のサッカーを見ているんだなあ、という気がいつもよりする。こういう気持ちでサッカーを見るのも、普段のしのぎを削って削って削りまくるようなリーグ戦とは別の楽しさがある。トップと比べてサテライトは数試合しかないが、こういう雰囲気をこれからも楽しめるということはとても嬉しいことだ。 こうして今年のフットボールシーンは、僕の周りだけでも今までに無いくらいの変化を見せようとしている。いろんなことが始まって、広がって、それらが全てつながりながら新たなひとつのシーンを作り上げようとしている感覚を覚える。プリンスリーグやサテライトはそんなシーンのひとつだ。そして、そんなシーンがありとあらゆるところで始まり、それらがどこかでちょっとずつつながり形作って、日常に次第に溶け込んでいくもの、それがこのコラムのタイトルの一部でもあり、僕が言いたい「FOOTBALL」と「LIFE」っていうやつだと思っている。フットボールだけじゃなくてもひとりひとりのシーンがどこかでつながり、また別のシーンを作り出し、それが緩やかな連鎖とともに変わり続けていく。嫌な事だってあるけれど、全てが嫌なことばかりではないし、ある変化が起こって、それが僕達のシーンに、そして僕自身にどう作用して僕の内面や外見がどう変化していくのか、それを考えると心配事は多いけれどもそれほど悪い気もしない。「ライク・ア・ローリングストーン」、もしくは「生々流転」ってところか。 僕自身にも大きな変化があった。一言で言えば、アウェイからホームへ。変化を楽しむということを本当の意味で出来なかったのであろう僕はここに戻って一休みして、再出発をするつもりでいる。さながら渡り鳥のような気分。そうして僕にかかわるいろんな変化を感じて、それを楽しんでいける存在になりたいと、そう思っている。そうしてあの宮の沢の雰囲気のように肩肘張りすぎずに緩やかに穏やかに、しばらくは過ごしてみようかと思う。来るべき新たな変化をもっと楽しめるように。そうして僕は新たな「シーン」に触れたくて、またスタジアムへ足を向けたい、と思うのだ。
posted by retreat |23:34 | classics | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年04月20日
aftertalk #41
clasics #41でした。日韓ワールドカップのときに感じた違和感というのは、ちょうどここから一年前のclasics #24でも目の当たりにして書いているんだけど、また一年経って思い出していろいろと。ワールドカップ真っ最中の時より感情がこなれて落ち着いてきているなあ。 あれからサッカーのすそ野は広がり、Jを目指すチームも、プロにこだわらず地域に根ざしていくチームも増えた。「ゆるやかに」なんてもんじゃなかった。あれから6年でJとJを目指すチームが何十も存在するなんてことはとてもじゃないけど思っていなかったし、もっとゆるやかに増えるものだと思っていた。おそらくJを目指すチームが飽和に近づいた今、これからは淘汰と選択(経営的なリスクを冒してもプロを目指すのか、アマチュアのままでチームを続けるのか、ということ)の時代が来るだろうと勝手に思っている。ちゃんとした根拠はないけど。 もうひとつ決定的に今と昔とで異なることというのがあって、それは「夢を見なくなった」ということ。この当時、もっとサッカーを見る人も語る人も増えていけばきっといいことあるはず、みたいなことを書いていたけど、今の自分は「こうなったらなんて素晴らしい世界になるんだろう」と思うことがほとんどなくなった。全くなくなったわけじゃない。近い未来についての夢というのは持っていて、けれどもそれは大きなことではなく、自分とその周りの世界に対するささやかな希望、のようなものだったりする。生活についてとか、仕事についてとか。見切りをつけたわけではないんだけど、なんというか、夢を見るのにも疲れてきたというか、自分の度量とかこの能力でできることがだんだんとわかってきて、それ以上のことを背伸びして求めようとしなくなったというか。成長したくないなんて思っているわけではないし、伸ばしたいところ、直したいところというのはそれこそ齢を重ねるごとに増えていく。とりあえず目の前に立ち並んでいるそれらをひとつずつ解決していくだけで精一杯で、そこから先のことなんて見る余裕はないし、見えるわけでもない。歳を取るってこういうことなのか、と改めて思う。自分は小さいときから「大人びている」とか「子どもらしくない落ち着き方」だとか言われていたけれど、そういうのはすべて表面上のことで、内面は他の同年代の子ども以上に子どもっぽかったんじゃないだろうか。そう考えると、自分は今まで大人に対して取り繕うことだけで生きていたんだろうなと考えてしまって、俺の人生何なんだと少し落ち込んでしまう。 あきらめるということはないけれど、自分の持つことのできる「希望」というものの大きさと量は確実に小さく少なくなっていっている。いつかすべてを無くしてしまうんじゃないかって、少し怖い。何もない人間になるということが怖い。いつか来るであろう「幼年期の終わり」っていうやつに、怯えるこの頃の自分だ。いつか自分にも、何かできるのだろうか。
posted by retreat |19:53 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年04月18日
CONSAISM clasics #41
clasics #41です。ちょうど日韓ワールドカップから一年後の話。 ちょっと肩の力が良い具合に抜けてて、個人的に好きな回。
一年前の5月31日、夜あなたは何をしていましたか? 一日の仕事を終えて、帰り道についていましたか。それとも家にいましたか。まだ仕事中でしたか。誰かと一緒でしたか。それとも一人でしたか。日本と韓国で開催されたワールドカップの開幕戦、王者フランスと、未知の国だったセネガルとのゲームを、どこで見ていましたか? はて、と僕は思い出すまでにしばしの時間を必要とした。このところ一年前の記憶どころか昨日の夕食の献立さえも憶えていないような健忘症っぷりなのでちょっとしたことが思い出せずに苦労することがよくあるのだ。・・・ああ、思い出した。あの試合は新宿で見ていたんだった。大画面に映されるとってつけたような開会式のあと、「ラ・マルセイエーズ」の合唱とそこに重ねて大写しにされたジダンの顔を見て、ああワールドカップなんだと実感したんだっけ。後ろの席にはドイツ人らしい一団がいて注文するのに難儀していたっけ。よくわからない若者が騒いでいたっけ。ジャパニーズ・フーリガン!とか叫んで。それに僕は気分を悪くしたんだった。うざったいからつまみ出してくれ店員さんなんて思ったりしていたんだっけ。そしてキックオフ。リズムをつかめないフランスに対して、開幕の緊張などどこにもないように奔放に、でも意外に統制の取れた試合運びを見せるセネガル。次第に気づいていく、フランスはリズムに乗れていないのではない。疲弊していたのだ、最初から。セネガルのゴールに、店の中では落胆と驚きがないまぜになった歓声があがる。4年前の輝かしいフランスはどこへ行った?と疑問符を頭の中に並べながら見ているうちに、開幕戦はどんでん返しの幕を開けて終わった。今になってもうまく形容できないでいる熱気がくだを巻き、僕を戸惑わせ、狂わせたワールドカップの始まりは、そんなふうだった。 あの一ヶ月、僕はどうせ行けないだろうと思っていたワールドカップの試合を生で見ることが出来て、「si se puede!」が僕の中での流行語になって、新宿で「テーハンミングッ!」の大合唱を聴いて、日本対トルコ戦では当たり前のように代表のレプリカを着て会社の会議室で試合を見た。青いシャツとイングランドの7番のユニフォームが日本中を塗り分けた。わけのわからない焦燥と無軌道な高揚感が日本中を突き動かしていたように思えた一ヶ月は横浜の夜に終わりを迎えて、みんな何事もなかったかのように普通の毎日に戻っていった。その「戻り方」のあまりにもあっさりとした切り替わりに僕はまた困惑し、その後に再開されるJリーグの行く末にちょっとした不安を抱いたりした。そんな流れの中で、一年後の事なんかわかりもしなかった。それよりも札幌の一部残留が全てに優先していた、という事実もあったけれども。 そうして一年後、である。なんだかんだと言いながらもJリーグの観客動員数は増え、サッカーに興味のある人が増え、何人かの代表選手は海外移籍を果たした。そこに深みは感じられないながらも広く浅く、なだらかにフットボールはその地平を広げていった。本当はワールドカップがあった一年前、僕はきっと日本のフットボールシーンはもっと大きく変われるものだとばかり思っていた。Jリーグはもっと盛り上がり、代表はもっと強くなり、もっとフットボールが楽しくなるとものすごくポジティブに考えていた。でも今になって、それは現実になったかというとそうではない。むしろ僕の浅はかさを助長して、自己嫌悪をちょっとばかり、いやかなり悪化させただけだった。まあ自分の考えが相当に甘かったってことなんだろう。そうそう自分の思うようになんか行かないし、総体としての世界は急激に変化することなどないのだろう。それがわかっただけでもオッケー、と思うことにする。 けれども僕はこれからもフットボールの世界において、こんなふうにポジティブに考え続けることをやめないだろうと確信犯的に思っている。いろんな街に大小問わずクラブが出来て、熱心に試合を見つめるファンがいて、フットボールが広がっていく。そんな妄想とも空想とも取られても仕方の無いような思いを、僕は止めることが出来ないし、止めるつもりも無い。それほどまでに僕はフットボールに憑り付かれてしまった人間になってしまったのだ。ボールはゴールに向かって前に進んでいく。なぜなら、それがフットボールだからだ。そして僕の人生も否応無しに前に進んでいく。なぜなら、それが僕の人生だからだ。そうして僕はゴールを奪われながらもゴールを決めるべく前に進む。取ったり取られたりしながらゲームは終わることなく続いていく。それが僕のゲーム。僕のフットボール。一年前も一年後も、今までもこれからも変わらない「前に進む」というポジティブな事実。それを僕はやっと実感しつつある。 この文章を書いている今日、札幌の天気はスガシカオの歌じゃないけれども宇宙まで突きぬけそうな青空で、僕が宮城スタジアムで「ワールドカップ」を体感したときもこんな汗ばむくらいの天気だった。メキシコ人もエクアドル人も日本人も、あの時あの場所にいたみんなが青空の下にいた。そして僕がこんなことを書かなくったって、青空はもの言わず続いていたのだ、ずっと。
posted by retreat |21:46 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月16日
aftertalk #40
clasics #40をお送りしました。こないだ「何書いてるんだかわからないシリーズ」と名付けたやつの第2回ということですが、まあそんなこと言っても毎回何書いてるんだかわからない内容ではあるんですがね。人生をサッカーに例えたり、その逆だったり、別のもので例えてみたり、そういう考え方を軸にしてここまで書いてきてるわけですが、この回は「考え方」そのものをテーマにして書いてます。「Life is Football」とか「No Football,No Life」っていう言葉がその昔からサッカーを語る巷にはあって自分もそういうのを使ってきたけれど、最近はそうも思えなくなってきた。もっと複雑で深遠な、入り組んでいて怪奇な、そんなものが人生には含まれているんじゃないかと。その思いをじっくり煮詰めていくと、とてもじゃないが人生をサッカーなんぞに例えることなんてのはすっかりできなくなってしまった。90分では収まりきれない、11人でも成り立たない。そんなシンプルなものでもないとずっと思っていたけど、サッカーに例えるとするとあまりにも単純になりすぎる。人生は人生にしか例えられないものだと思うようになった。 それでもサッカーにはあのピッチとスタジアムでしか表現できない、何ものかがある。だからサッカーを見ているし、これからも見ていくんだろう。人生の中にサッカーがあるのでも、サッカーの中に人生があるのでもなく、また同時にそうとも言える。渾然となって存在しているとも言えるし、それぞれ全く別の存在によっているということも言える。それこそ「Life is Football」とか「No Football,No Life」のように、この世の何事をも一言で例えられるような言葉というのは実は存在しないのではないだろうか。存在しないというよりも、「それ以上」の範疇で語ることができない、そういうことかもしれない。人間が発明したスポーツを語るには人間の発明した言葉では足りない、もしくは人間の言葉では足りないほどの存在になってしまった。言葉も人種も住む街も飛び越えてひとつのボールを共通の存在にして、みんなでボールを追いかける、そんな世界というのはなかなかに楽しい。言葉にしなくても、蹴るだけで、もしくはそれを見つめることで気持ちの伝わる世界だなんて、こんなに幸せなことはない。
posted by retreat |22:02 | aftertalk | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月15日
CONSAISM clasics #40
clasics #40です。前回の「classics」に続き、「何書いてるんだかわからないシリーズ」第二弾。
言葉というのは不思議なもので、自分ではうまく言い表せなくてもどかしいことをたった一言で言われたり、あるいは読んだだけで愁眉を開くような、雷に打たれたような刺激を受けた経験のある人は多いと思う。(ちなみにそんなことない、という人はすごい人だと思う。その理由はまた後で。)その最たるものが「人生とは〇〇である」という例えの言葉だろうと思っている。曰く、「人生とは登山である」「人生とは川の流れである」「人生とは天気である」、そして僕がこうして書いているコラムで何度もしつこく言っているように、「人生とはフットボールである」とも。(ちなみに、「人生とはフットボールである」ということと「フットボールとは人生である」ということは、主語とその対象を入れ替えただけではとどまらないもっと大きな違いがあると感じているが、そのことはまだ自分の中でもまとまっていないので改めて書いてみたいと思っている) こうして人生というもの(なんだか上段に構えているようで気恥ずかしい、と思う人は「人生」を「日常」とか「生活」と読み換えてみてください)を一つや二つの簡単なセンテンスに丸め込んで表現するということは確かにわかりやすい。また、はっきりとはわからなくても「ああ、そういうことかもしれないよな」なんて、なんとなく納得できたりする。どうしてそういうふうに納得できたりするのかというと、そのように人生のメタファーとして置き換えられるものというのは、必ず今この世界の中にある何ものかであり、思想であり、物体であるからだ。人間が今までの歴史の中で誰も思いもつかなかったようなことをとりあげて「これが人生というものだ」――なんて一刀両断に言うことはまずないし、あったら人間なんて生きることに飽きてもう存在すらしていないだろう。だって人間は「それ」を思いついたことがないのだから、それはどっちかというと「発見」に分類されるものだろう。そうして人生というものは、そのメタファーにされる対象によって如何様にもその読み取られる形を変えることができる。複雑な多面体、もしくは不定の流動体をいろいろな切り口でいろいろな角度から眺めるようなものだ。それは硬質であると同時に柔らかであり、熱いところも冷ややかな部分もあり、いつもどこかしら不透明で、めまぐるしくその形を変えているものだ。そういう存在が人生であり、またフットボールでもあるのではないか――と、また僕は小難しく思ったりしている。 まあそういう思考はともかくとして、ここで僕にはひとつの思いが生じてくる。「人生とは〇〇である」と例えることによって、人生というものをシンプルに提示することはできる。しかしそこで一言にシンプル化されることによって、語られることのないいろんな感情や事象が出てきてしまうということだ。砂を両手にすくったとき、手のひらからこぼれおちてしまうように。そうしてこぼれおちたものは「人生とは〇〇である」という、理解する側にとっては圧倒的な言葉の威圧感の前にその存在感を希薄にさせられ、その言葉を受けた瞬間、それに気づくことはまずない。それゆえに、一言では言い切れなかったこぼれおちたものを別の手で受け止め、提示するために「人生とは〇〇である」というような、さまざまな表現が成り立つことができるのではないだろうか。 ゆえに「人生とはフットボールである」と言う表現もまた然り、だ。人生という長いスパンのものを90分のフットボールに例えることの中で、自分でも気づかなかったほんの小さな感情の揺れ動く様を読み取るということは非常に困難だ。朝、道ばたに咲いていた花の美しさを「フットボール」という例えを用いて表現することはちょっと難しいかもしれない、ということだ。まあ、人生の全てをフットボールに例えることができたとしたらそれはそれで悲しむべきことなのかもしれない。俺の人生ってその程度だったのかよ、なんて。 ということで、フットボールというものの中にはまだまだ僕らが語ろうとして語れないもの、感じ取ろうとして感じ取れないもの、表現しようとしてできないもの、あるいは想像もしていなかったようなものがまだまだ隠れている、と僕は思う。そしてフットボールを観て、語るということにはそういった隠れている(あるいは見過ごしていた)ものを拾い出し、感覚として共有することを大きく広げる可能性があるではないだろうか。ゼノンが「アキレスと亀」の論法の中で示したように、時間は無限に分割されることができる。だとするならば、フットボールという事象においても「時間」を無限に分割し眺めることができるのだろうし、そこには無限の意味がある。そしてそれはフットボールにとどまらず、他の人生のメタファーとして表現されるもの全て、ひいては人生そのものに広がっていくのではないだろうか。とはいえ、これはちょっとかなり乱暴な言い分だとは思うけれども。 そういうわけで冒頭でもちょっとだけ触れたが、たった一言の言葉で愁眉を開く、もしくははっとさせられるような経験をしたことがあるか、と聞かれて「そういうことはない」と答えた人は個人的にすごい人だと思う。それはつまり「人生とは〇〇である」というように、この世の全ては一言で表すことなどできない、ということをもうすでに獲得できている人なのだろうと思うからだ。そして僕はそういった経験がなかったので、人生をフットボールというメタファーにして、こうしていろいろと考えてみたりする。 まあ毒にも薬にもならないだろうが(もしかしたら毒になる確率が高いかもしれないが)、こういうことを考えるのは僕にとってはとても楽しい。だからこれからもフットボールの中に見えるいろいろなものを眺め、また見出していければいいと思っている。それが僕にとっての、フットボールを「観る」という行為だ。
posted by retreat |00:09 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)