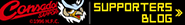2008年05月19日
CONSAISM clasics #50
clasics #50です。これにて一応連載は最終回。
「ハルウララ」という名前の競走馬をご存じだろうか。最近ニュースに取り上げられている「100連敗の競争馬」のことだ。 高知競馬に所属する7歳牝馬の彼女は95戦を過ぎた辺りからマスコミに取り上げられるようになって知名度が一気に高まり、彼女とそれを取り巻く人々のドキュメンタリーが放送され、100戦目には東京からの観戦ツアーも出た。競馬場ではTシャツや尻尾の毛を入れた交通安全のお守り(買っても馬券が「当たらない」から、車にも「当たらない」という意味で)といったグッズまで販売されている。 けれどもハルウララの人気は連敗続きであるということだけではなく、体も小柄で気が弱い、そんな馬でも競走馬として一戦一戦一生懸命に走っている、その姿に心を打たれるファンが多いからだという。リストラに遭った人や単身赴任の人、病気と闘う人……そんな人たちが彼女の走る姿に励まされている、ということを知った。 ひたむきであるということは、ただそれだけで人の心を打つことがある。 僕は一時期競馬にすっかりはまっていた時期があった。今では年に数回馬券を買いに行くだけになってしまったが、最盛期は毎週のように競馬場や場外馬券場に通いつめ、中央競馬だけでなく高知競馬のような公営の、俗に言う「地方競馬」に属する道営競馬に顔を出した。贔屓にしていた競走馬なんかもいて、その馬の馬券をずっと買い続けたりもしていた。運が悪いのか自分の推理が足りないのか、馬券が当たることは少なかったがそれでもどの馬が強いのかを新聞片手に検討し、決めた予算の中でやりくりして馬券を買い、そうして臨んだレースごとに一喜一憂できればまだ良い方でだいたい一喜十憂くらい。 けれどもフットボールの魅力に取り憑かれたのち、僕は次第に競馬場からスタジアムへと足を向けるようになり、フットボールと札幌の応援に深くのめり込むのと反比例するように競馬への興味は薄れていった。そんな中、ハルウララのニュースは昔熱中した競馬のことを少し思い出させてくれるとともに、厳しい公営競馬の現状をも僕に知らしめることとなった。 JRA(日本中央競馬会)が運営する中央競馬においても馬券売り上げの減少に苦慮している現状ではあるが、それに比べても各自治体が運営する地方競馬はどこも苦しい経営を余儀なくされている。ここ数年でやむなく廃止となった地方競馬もいくつかあり、またそれはハルウララの所属する高知競馬においても例外ではない。約88億円にのぼる累積赤字を県の負担にして一旦帳消しにしたが、今後四半期ごとに経営状況を公表して、赤字経営になると即廃止になるという。 競走馬の一大産地である地元・道営競馬でも開催競馬場の縮小やコスト削減に努めているが、188億円(※)という膨大な負債を抱えている。また生産者側においても能力を秘めながらも血統や馬体が目立たないがために高値で馬主に売れなかったり、生産規模を縮小するなど対策をとってはいるが、近年の不況による売り上げの低下も加わって地方競馬をめぐる状況は一層厳しくなっているのが現状だ。勝てなくても走り続けるハルウララはむしろとても幸せな方で、ピークを越えた馬たちは次々に競馬場を後にして「処分」される。走る馬たちも、それを育て鍛える調教師たちも騎手たちも、経営する自治体にとっても厳しい日々が続いているのだ。 ここまで考えてみると、この状況は今の札幌によく似ているのだ。中央(J1)と地方(J2)の格差、多額の負債、「見て見ぬふり」をしてきた経営状況……。 けれどもただひとつ高知競馬と異なっているのは、ハルウララのように誰からも愛され、応援する気にさせてしまうようなひたむきな存在をどうしても見いだせなかったことだ。今年の僕は最初から最後までどこか猜疑的な視線で札幌を応援していたと思う。どこからかもやもやとした疑問が首をもたげてきてチームを信じられなかったのだ。いや、どこも信じられなかった、と言った方が正しかったのかもしれない。そのぶん自分を信じることで、それを声援として伝えることで乗り越えることができたらよかったのだけれど、胸に手を当てて考えてみるとそれすらもできていなかったのでないかという念に駆られる。先日発表された再生計画や補強の動きも、それを打ち消してくれるには現在では不十分なままだ。おそらくこの不安な気持ちは年を越してしまうことになるだろう。 道営競馬も札幌も今までのツケがもたらした「負のスパイラル」を断ち切るべく行動しているし、それはこれからの未来のために必ず断ち切らねばならないものだ。しかし結果と利益が求められるフットボールビジネスの世界とは言え、良い意味でハルウララのような、ひたむきに走るその姿だけで応援したくなるような、そんな存在が札幌に現れて欲しいと思っているし、そんな光景にこそ僕らがチームを応援したくなる原風景としてのフットボールが、すべての原点が眠っているのではないだろうかと思っている。まずはその「原点」をもう一度見つめることから2004年のシーズンは始まるのだろうと思う。もう一度やり直す、そして失敗の許されないただ一度きりのチャンスが始まるのだ。 来年はいろいろな場面で大きな転換が訪れるだろうということはうっすらと見えてきている。「来年からは」と心機一転を求める気持ち、「来年こそは」と雪辱を求める気持ち、このふたつの気持ちを持ち続けていかなければならない。そのための「原点を見つめ直す」時間は幸いにも与えられたのだから、肩肘張るのではなくむしろそんなことを楽しさに換えていければいい、と思いつつ僕の2003年は暮れようとしている。 来年は良い年になりますように。 (※金額は2002年末時点、うち北海道171億円・北海道市営競馬組合17億円)
posted by retreat |23:11 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年05月15日
CONSAISM clasics #49
clasics #49です。終わりが近づいている頃の思い出話。
夏の終わり頃に、話はさかのぼる。 週末に旭川に行っていた父が一枚のユニフォームを手に家へ帰ってきた。黄色と青を基調としたスウェーデンカラーのユニフォームだ。 胸には父の出身校、そして袖には「創部50周年を祝して」の文字が入っていた。背番号は11番。父は旭川へ、高校生当時に所属していたサッカー部の50周年記念の祝賀会に行ってきたのだった。背番号11は、父が当時つけていた番号である。 昔から父がサッカーをやっていたということは折々に聞いていたが、こうしてユニフォームと50周年の記念誌にある父の写真をみると、ああ本当にサッカーやっていたんだなあと改めて思わされた。その夜は父と僕とで、少しばかり昔のサッカーの話で盛り上がった。 父がサッカーをやっていた当時はいわゆる「WMシステム」の走りの頃で、左利きで運動量のあった父は主に左サイドハーフと左ウイングでプレーしていた。現代のシステムで言うとダイヤモンド型の中盤の左サイドと3トップの左、と言えるだろうか。昔は芝のグラウンドなんて北海道になかっただろうから当然土のグラウンド、スパイクを買うお金にも苦労していたその頃は一足のスパイクを大事にはき続けていた。雨が降ればグラウンドはドロドロになり、そんな中で泥にまみれながらもボールを追いかけていた。ちなみに当時のユニフォームはオレンジを基調としたデザインで、今回創部50周年記念のユニフォームがスウェーデンカラーのユニフォームとなったのは、単純に「安かったから」という理由らしいけど。 50周年記念誌を紐解くと、父がいた当時のサッカー部はなかなか強かったらしく、地区代表として高体連や国体の北海道大会に何回か進出している。残念ながら近年はなかなか勝ちあがれないようだ。 その高体連や国体の道大会に出場していたことを示す年表を見ていると、一つだけ「出場辞退」と書かれていた年があった。ちょうど父がサッカー部にいた頃だ。なぜ出場辞退になったのか、ということを父に聞くと、 「出席日数が足りなくて、道大会に行くことができなかったから辞退した」 と話した。さらに続けて、 「確かそのころはなあ、俺は働きに行ってたんだよ」と言った。 父の実家は兄弟が多く生計を立てるのが苦しかった、だから小学生の高学年の頃にはもうアルバイトをしていたんだ、という話はよく僕も聞かされた。でも学校をこんなに長期間休んでまで働いていた、というのは初めて聞いた話だった。そこまで生活が苦しかったとは、正直僕は今まで思っていなかった。それと同時に、そこまでしてサッカーを辞めなかった父は本当にサッカーが好きだったんだなあ、としみじみ思った。サッカー部の頃の話になると、普段の父の表情とはまた異なって、楽しそうに、懐かしそうに相好を崩すのだった。 父の知らない一面が見えたなあ、と僕は思った。父は僕の想像もつかないくらいにとても苦労して、でも父なりに楽しい高校生活を送っていたのだ。そういう苦労した姿を見せない父の背中の強さを改めて思い知らされた僕は、自らの鬱屈した高校生活を顧みて自己嫌悪に陥ってしまった。僕にとっての父は、ある意味で未だに超えられない存在なのだということを改めて思い知らされた気がした。 僕と父がひとしきりサッカーの話をした後、僕がしきりにいいなあそれ、といっていたスウェーデンカラーのユニフォームを手にとって「お前にやるか?」と尋ねた。僕が好きでいろいろなユニフォームを集めているからだろう。でも僕は最終的には「いや、いいよ」と答えた。 たとえ昔と色が違えども、父が持って帰ってきたそのユニフォームは確かに父が泥まみれになってグラウンドでプレーした、一つの時代の証なのだ。それを簡単にもらってしまうのは、父の過ごした時代の一部分をを勝手にむしり取ってしまうような気がして、それを考えるとやはり父が持っておくべきなのだ、と思ったからだった。 今でも父は体を動かすことが好きで、ランニングもするし、冬になるとよくスキー場に通うし、本人はあまり好きではないようだけどゴルフも上手い。そんな父からスキーや水泳の手ほどきを受けたこともあった。けれど思い返してみれば、サッカーボールを蹴って遊んだ記憶はなぜだか薄い。そのことはまだ、本人に確かめられないでいる。 そうしてスポーツだけでなく、人生そのものにおいても父という存在は僕にとって一つの目標であり、羨望であり、時には憎しみであったりする。たぶんこの気持ちは一生消えることはないだろう。だからこそ僕は僕で僕なりに人生を築きあげなければいけないのだろう。それが肉親のものであれ、いつまでも誰かの影を追いかけて生きていくことなどできないのだから。 そんな話をひとしきり聞いた日の夜、僕も父のように昔のことを語る日が来るのだろうかと考えた。いつかのある日曜日の夜に、赤と黒のユニフォームを見せながら「昔はなあ、鳥居塚っていうすごい選手がいてなあ」なんて子供や孫に語る日が来るのだろうか。そんな僕の姿を想像して思わず失笑してしまった。そんな時代は僕にとって遙か未来の話に思えて、あまりにも現実味がなさすぎて、それでもそんなことを考えている僕が滑稽で。 しかし、ものすごく長い目と想像力をもって考えてみると、僕が札幌を応援しているのはいつかそういう日が来ることを信じているからじゃないだろうか。誇りと愛を持って語ることのできる未来を願っているからじゃないのだろうか。 僕らがこれから向かう札幌の未来は決して簡単なものじゃなくて、むしろ苦労の多い時代になるかもしれない。でも、それもすべては輝かしい未来のためだと信じていたいし、それを現実としていきたいのだ。
posted by retreat |23:15 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年05月11日
CONSAISM clasics #48
clasics #48です。自分の応援の原点と、一冊の本の話。
以前にも書いたことがあるが、自分がこうして応援に関わっていくことの「原点」ともいえる体験は、中学3年の時の中体連にさかのぼる。 校則を無視して改造した学ランを堂々と来て体育館のど真ん中にどかどかと走り込み、あらん限りの声と覇気で部員にエールを送る。そのわずかなひとときだけ、好奇と失笑を含んだ全校生徒の目が自分を含めた応援部に注がれる。 その「見られる快感」が忘れられなくて、高校1年の時、今度は運動会のために選ばれる組別の応援部に参加の手を挙げた。 しかし高校の応援部は、いわば半分お遊びの中学とは段違いだった。毎日裸足でくたくたになるまで、日が暮れて闇に包まれるまで練習を繰り返し繰り返してやっと「戦力」となることができた。それだけ濃く過ごした日々があった分だけ、応援をする時の快感と、全てをやり終えた時の充足感や達成感は泣けるほどに込み上げてきた。 やっぱり応援ってのはいいもんだ、と思ってしまった僕は、それから2年後に厚別のゴール裏へ足を運ぶようになってしまった。とにかく応援したかった。 何で今さらこういう思い出話をしているかというと、最近読んだ本が僕の記憶を呼び起こしてしまったからだ。 「東京大学応援部物語」というのが、その本の題名だ。最高学府の東京大学にあって、「応援」に学生生活のほぼ全てを捧げ、厳しい規律のもとに最後の最後まで必死に応援を繰り出す。東京六大学野球の最終回、たとえ19対0で負けていても逆転を信じて疑わない彼らや彼女らたちの姿が描き出されたノンフィクションである。 応援部の舞台は東京6大学野球、神宮球場を中心に描かれる。弱いことで有名な東大野球部にあって、1勝のため、1アウトのため、1ストライクのために拳を突き出し、声を枯らし、日々の練習はともかく合宿まで行なう。 年功序列の理不尽に悩み、応援することの意義に悩み、理想と現実の矛盾に悩む。それでも彼らや彼女らは応援することを止めない。 それはどうしてなのか。自己満足か、自己犠牲か、純粋な憧れがあるからか。それぞれの応援部員の姿が浮かび上がってくる。 そしてこの本を読んで一人でなんだか高揚してしまった僕はそのまま室蘭(10月25日・大宮戦)まで行ってきて、いつもより余計に意気消沈して帰ってきた。もはや内容云々をいえるレベルではないところまで札幌は頽廃していた。勝ちたいという意識がピッチから微塵も伝わってこずに、どうしたものかとため息ばかりを雨の降る室蘭の空にいくつも吐いた。 確かに学生野球とプロスポーツのそれとでは異なるところがいくつもある。プロとしての「興行」である以上、選手はプレーを通じて観客に見せるものがなければならないし、学生野球は学校や選手それぞれに目指すものが違う。応援だってゴール裏で応援することは完全に自由意志だけど、応援部で応援することは時に強制という名をとりつつ行われる義務になる。けれどもそんな理屈はもう今の札幌には通用しないのかもしれない。改めて「何でこんなチーム応援してるんだろう」と自問自答しながら家路についた。 ただどちらにも通じるのは、日常では味わうことのできない喜怒哀楽がそこに詰まっていることではないだろうか。 一つのプレーの行方にあれほどまでに熱中して、我を忘れるほどに驚喜できることがあるだろうか。あれほどまでに仲間や友人を得ることができただろうか。あれほどまでにまっすぐに馬鹿みたいに、ただ一つの勝利だけに叫び、悩み、信じることができただろうか。交通費とチケット代を借金してまで用意して得られたものは、その金額だけでは計ることなどできないものだった。 だからこそ今の札幌の負け続け、自分を見失い、戦意のない姿がどうしても許せなかった。 この本の中で、著者がある応援部員に、 「応援で得たものはなんですか」 と問いかけるシーンがある。それに対して彼は、 「得たものは、自分の未熟さを知り、自分の弱さや卑怯さを自覚することができたこと」 と答える。 これはプレーする側にも言えるのかもしれないと思う。一つ一つの試合と練習を重ねる毎に自分の未熟さを知り、それを克服しようとする。その姿が見られるからこそ僕はしつこくしつこく競技場へ足を運ぶのかもしれない。 でもそんな姿を見ることができない最近のチームをどのような思いで見ればいいのか、と思いながら僕は今季最後の厚別(11月1日・新潟戦)へと足を運んだ。 ところがそんな僕の予想に反してチームは戦った。数的不利も審判の曖昧なジャッジにも耐えて、首位の新潟を相手に勝利に限りなく近いドローに持ち込んだ。厚別のピッチの上で選手たちが意識を高め、水際で新潟の攻撃を防ぎ、果敢にドリブルで持ち上がり、ライン際のボールを我がものとするために体を張っていた。 こういう姿が観たかったんだ、と僕は拳を握った。その気持ちと同じだけ、心の裏では、「やれるんなら最初からやっとけよ」とも思ったけど。 プレイヤーとして必要とされる技術や運動量はトレーニングでその人の限界まで高めることができても、その人の意識は自分が自分の内にある弱さやずるさや甘えに本当に気付いて、それに対峙しない限り高めることはできない。けれども、誰もが抱えているその葛藤をじっと見つめ、それに立ち向かう姿があるからこそ、僕らはスタジアムへ通い続けるのではないだろうか。そして、その姿を見せてくれるのがプロと呼ばれる人たちであってほしいと、勝手ではあるが思っている。残り3試合、そんな姿を少しでも多く見せてほしい。それが未来へ続くのだと僕は信じて疑わないし、僕にとっての応援したくなる原動力なのだから。 *参考文献 最相葉月著「東京大学応援部物語」(集英社)
posted by retreat |23:00 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年05月08日
CONSAISM clasics #47
clasics #47です。積もり積もった怒りがここに来て爆発したのか、なかなかエキセントリックな文章になっています。
J1昇格への路もあっという間に消し飛んで、来期がどうこうといった話が厚別へ向かう僕の耳を通り過ぎていく。予算は10億で人件費3億、若手中心の編成で、外国人はゼロになるかもしれなくて、有望な若手は他クラブへ移籍……。秋晴れの土曜日であっても現実は容赦なく冷たい風を吹かせてくる。 4得点を挙げての鳥栖戦の快勝も、そんなこれからの話を考えるとつかの間の歓喜でしかなかった。この先には冷たい現実がじっとこのチームを待ち構えているのだと思うと、こういう試合ができるならさっさとやってくれれば良かったのに、なんてネガティブな感情だって自然と出てきてしまう。 鳥栖戦は有り体に言えば勝利以外に見受けられるものはなかった。来期は若手中心と言いながらその顔ぶれには若手は少ない。監督が代わって10試合以上経つのに、はっきり見えてこない戦術。退場者を出して劣勢の中での勝利だったとはいえ、そこに僕が今一番見たい「これからの札幌」は見えてこなかった。 そんな試合の中でも僕の心臓がどくんと波打つ瞬間はあった。 ボランチの森下が、アンドラジーニャの退場で一人少ない分を埋めようと、とにかく前へ出てプレッシングをかける。中盤深くからどんどんとボールを追いかけて相手GKへのバックパスまで追いかける。その姿にスタンドからは自然に拍手が湧いてきた。そう、そういう姿が見たいんだ、とでも観客が主張するように。 あの状況で森下が激しく動いてくれなかったら、おそらく札幌の守備ラインはずるずると下がり間違いなく鳥栖にゴールを許し、連敗していたこの前までのようにネガティブな悪循環に陥ってしまっていただろう。そういう意味で他の選手達にも、前から守るという意識をしっかり見せたと言う意味では職人肌でプレーで伝えるタイプの森下らしいやりかただな、と思った。どこまでも迷走し続ける札幌にあって、そのシーンだけはちょっとだけ未来が見えたような気がした。 それでも試合終了の笛が鳴ったとき、僕は二、三回ほどの拍手をすることしかしなかった。やれやれ終わったなご苦労さん、という感じで。そんな醒めた感情しか湧いてこないのが今の僕の真実だ。 96年の高揚、97年の充実、98年の悔悟、99年の挫折、00年の歓喜、01年の満喫、02年の混乱、そして03年は「失望」という言葉がぴったりくるような感じがする。この間、僕はずっとゴール裏で応援してきて、今年はいろいろとあってゴール裏に行ったのは一度きりで、そうして僕がチームを見る方向もちょっと変わってきている。 僕はサッカーを見るにつれて一つの思考を固めてきた。それは、「サッカーは人生の縮図であり、現実の投影だ」という考え。現実に一つ一つ目標を明確に定め、クリアし、再び次の目標に向かってしっかりと階段を登るのにも似たトレーニング、それをクリアするため、より強くなるための試合というハードル。リアリスティックに過ぎるかもしれないけれど、そんな一つ一つがチームを強くするのであって、現実をすっ飛ばした夢や希望だけでは飯は食えない。 しかし今年の札幌はまさに「現実をすっ飛ばした」チームだった。ビッグネームの監督や選手に夢を見て、綺麗にあっさりさっぱり打ち砕かれた。 その後で今度は僕らに「5ヶ年計画」という名のもっと長い夢を見せてこの場を凌ごうとしている。明確なビジョンも見えないのに、より長い夢を無理に見させて僕らを忍従させようとしている。 僕らはもういい加減に夢と現実の境界線からはっきりと現実の側に立ち、冷静に判断しなければならないと思う。何が必要で何が必要でないのかをはっきりチームと認識し、共有し、育むこと。それこそが今いちばん大事なことだと思う。このままではチームの思うがままに思考停止のまま5年を過ごすことになると危惧している。現実になる可能性のとんでもなく低い、都合のいい恋愛ゲームみたいな夢を見ているまま僕らは冷凍保存させられて、吸い取るだけ吸い取ったら捨てられるただの一栄養体として、「マトリックス」みたいな世界でサポーター的一生を終えることになる。日本ハムの移転で札幌が確実に得られるファン層も少なくなる。そうしてこのまま僕らは乖離した夢と現実の狭間を漂いながら、ただただ虚ろな目でピッチを見つめるだけの人間機械と化してしまうのだ。 そんなチームに、誰が愛情を注げようか! サポーターとチームは一身同体だなんて冗談もいいところだ。都合のいいことばかり並べ立てて現実を乗り越えようとする姿を見せない怠惰で緩慢なチームなど、誰が応援できようか! 今、札幌は史上最大の危機を迎えていると言っても過言ではない。それは今まで甘い甘い夢を見続けてきたツケが雪崩を起こすように襲いかかってくる危機だ。札幌のサッカーだけでなく、北海道におけるプロスポーツの世界の危機だ。 僕らはその「現実」を乗り越えていかなければならない。現実を乗り越えなければその先の未来なんてないのだ。もしこのチームを少なくとも普通にフットボールの楽しめるチームにしたいのなら、今こそはっきりと現状に「NO」をあらゆる形で突きつけて、今乗り越えるべき問題を現実として共に認識しなければならない。 ジュニアからトップまで、ホームゲームの運営費から宮の沢の芝一本まで。そこまで考え、その上で目標を明確にするのなら、10年でも20年でも僕はこのチームについていこう。しかしそうでないのなら、チームに関わる全ての人々はスポーツというものに対して、そしてそれをとりまく社会に対して重大な背信行為を負うことになるだろうと思う。 だからこそ、今、声を挙げなければ、もしくは挙げ続けていたのならば無言の抗議をしなければならないと思うのだ。 だからこうして僕はこの文章を書いている。これが今僕の成しうる最大の声であり、武器だからだ。 僕はこのチームが真の意味で戦う姿を見たい。激しくボールを追い、ゴールを求める姿が見たい。サッカーで楽しみたい。スポーツで少しでも多くの幸せを得たい。 このチームにこんな思いを抱くことも、許されないのだろうか?
posted by retreat |01:21 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年05月04日
CONSAISM clasics #46
clasics #46です。そろそろこのコラムも終盤にさしかかっています。
いつからか、「がんばれ」と声をかけること、声をかけられることをなんとなく嫌うようになった。正確にいつからということは言えないけれど、たぶん中学校の時からこのような感情はあったと思う。 例えば毎年恒例のマラソン大会。僕は足が遅いながらもとりあえずよたよたと走っているときに、沿道からかけられる「がんばれー」という声。抑揚のないべったりとした声。 そんな声をかけられると、僕はたまらなく嫌な気持ちになる。何が「がんばれー」だ。こちとら窒息寸前でようやく走ってるというのに、そっちはのうのうと座ってるくせして。 とりあえず声かけとけみたいなおざなりな声援、いや声援とも呼びたくない。ただの記号、ただの音。そんな声を聞いたってこっちのやる気が削がれるだけだ。もうシオシオだ。頭に来る。だからその声を聞きたくなくて、そこから逃げたくて、僕は走るピッチを上げていた。この声を発した主がたとえ学校一のアイドルであろうと、一番の友達であろうと、「がんばれ」なんて言われたくなかった。「がんばれ」と言う側と言われる側の立場のギャップがあまりに耐えられなかったからだ。「がんばれ」という言葉が、言われる側に余計にプレッシャーを与えてしまうだけだと思っていたからだ。 そりゃあ確かに足は遅い。持久力だってない。そもそも運動神経が劣っている。それでもそれなりに走っているのに、言うに加えて「がんばれ」かよ。これ以上心臓に負担をかけろというのか。もっと言うなら殺す気か。そんな気持ちが僕のどこかに巣食っていて、以来「がんばれ」と意識的に声を出したことはほとんどない。 そんなのただのひねくれだ、ひがみ根性だ、偏屈だと言う人もいるだろう。素直に言葉を受け止めろ、と言う人もいるだろう。実際僕自身もそう思う。でもそれがまたどうしようもなく嫌なのだ。せめてもっと具体的に「足を上げて!」とか「もっと脇を締めて腕をふって!」とか具体的に言われた方がタイムも縮んでいいんじゃないのか? そんなわけで、札幌の応援をしている時や、他のスポーツを見ている時にも、「がんばれ」とはほとんど言っていない。そんな言葉でプレイヤーへの余計なプレッシャーを増やしたくないから。とりわけ「がんばる」ことが大前提のプロスポーツでは言いたくない。 それを観ている側として「がんばれ」としか言えないのは、あまりにもスポーツを知らなさ過ぎるからなんじゃないだろうかと思う。より良い結果を出すために、自分の能力を最大限に生かすために応援の言葉はかけるべきであって、それを言葉にできない時があるからこそ歌が生まれ、リズムが響くのだと思う。そんなことを、栗山でユースの試合を見ながら考えていた。 いいプレーをした時には「○○、ナイスプレー!」と叫んだし、一対一の勝負をためらう選手には「○○、タテに行け! 勝負!」と叫んだ。そういうふうに声を出していくことによって、初めてゲームに参加するということができるんじゃないだろうかと思った。そしてそういうことがプロスポーツを観る側においての敬意であり、また流儀ではないだろうか。「私たちはあなたたちのプレーを真剣に観ている」という意思表示においての声援。それはプレイヤーと観客との間に「見る」「見られる」といういい意味での緊張状態を作り出し、それがまたプレーを向上させる効果をもたらすのだと信じている。それがあって初めてスタジアム独特のあの雰囲気や、そのスポーツにしか感じられない醍醐味を共有することができるのだと思う。 けれども、「がんばれ」という言葉を全否定することはどうしてもできなくて、どうしても「がんばれ」としか言えない瞬間があるのもまた事実。 それは、スポーツが、身体の躍動が、言葉を超えてしまう瞬間。それをとりまく雰囲気や状況が「がんばれ」以外の声を本能的に否定してしまう瞬間。そんな時には「がんばれ」と思い切り言っていいんじゃないかと思う。ありったけの声で、ありったけの力で。そうとしか言えないことを自覚して、言葉を放つ責任を持って。 そう、全ての放たれた言葉には声を出したその人間の責任を内包している。それはすなわちスポーツの世界においては「真剣に試合を観ること」や「観客としてスポーツに参加すること」への責任、ということになると思う。果たしてそれが自分はできているだろうかと思っては、まだまだだなと痛感することしきりのこの頃。 今の札幌にかける言葉は何が一番いいだろう、と考えた時、「がんばれ」とはまだ言いたくないし、言えない気持ちがある。このチームにはまだまだやれることがあるし、まだまだ言える言葉が残っている。それは裏を返せば「可能性があるチームだ」ということでもある。J1昇格という言葉も他愛無い戯言になっているこの時だから、僕はこう言いたい。 「自分の持てるすべての力を発揮して、勝ってくれ」と。
posted by retreat |22:09 | classics | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年05月01日
CONSAISM clasics #45
clasics #45です。思い出深い国際ユースサッカー、忘れられない10分間のロスタイム。
先日行われた「2003北海道国際ユースサッカー大会U-16」を観戦してきた。 ユース年代の選手たちが国際経験を積む舞台として2001年から国内外の4チームで行われていたが、今年は「2002FIFAワールドカップ開催1周年記念事業」ということで、参加チーム数も6チームでの開催となった。 参加チームは地元・北海道選抜と日本代表U-16、ワールドカップ共同開催国の韓国からソウル特別市U-16、ドイツ・ミュンヘン1860U-16に加え、ブラジル・グアラニU-16、そしてスペイン・エスパニョールU-16。コンサドーレ札幌ユースからも北海道選抜にU-18の選手7名が、日本代表にも1名が選ばれた。 最終結果はグアラニU-16が日本代表U-16とPK戦にまでもつれ込む接戦の末に優勝したのだが、8月14~17日の4日間、計8試合(1試合は寝坊して観られなかった)の中でどうしても忘れられない試合があった。それがエスパニョールU-16対日本代表U-16の一戦。その試合のことからまず書き始めたい。 前日、ソウル特別市選抜に引き分けたエスパニョールは、この試合に勝たなければ決勝進出の可能性がなくなる大事な試合だったが、前半6分に日本代表DFのクリアミスをついて先制する。しかしソウル選抜戦よりも遥かにプレーが荒く、ファウルを取られるシーンが数え切れないくらいになっていく。とにかく強く当たり、後ろからでも平気で削り、ボールをとにかく奪うことを目的としたプレー。これが本当に16歳のする試合なのか、と思ってしまったくらいの荒さ。 その結果、前半33分にはイエローカード2枚で早々とエスパニョールの選手が退場となってしまう。数的優位に立った日本代表は押し込むが、守りを固めたエスパニョールDFを崩せず、さらにラフになっていくプレーにお互いの苛立ちが隠し切れなくなっていく。 判定への不満をアピールすることが多かったエスパニョールはその怒りがプレーにもますます顕著になり、後半16分、さらにもう一人の選手がレッドカードで退場処分となる。 そうしているうち、エスパニョールベンチの方から何か物が鈍くぶつかるような音がやまないと思って見ると、ベンチに下がった選手やコーチがそのやるかたない怒りを椅子や壁を蹴ったり殴ったりしてぶつけている。それほどまでにエスパニョールは感情のコントロールができなくなっていて、つまり怒りのあまりに「切れて」しまっているように見えた。 しかしこの退場劇で日本代表は気が緩んでしまったのか、後半27分にエスパニョールが再度相手のミスをつき追加点を挙げる。狂喜するエスパニョール。呆然とする日本代表。 だが、ここから日本代表の大逆転が始まる。途中出場のマイク・ハーフナー(前札幌U-15、ディド・ハーフナー元札幌GKコーチの長男)が左からのクロスに合わせてヘッドを決めると、後半44分にはFKを再びヘッドで叩き込み同点に。 このまま引き分けになるのかと思われた瞬間、第4審判の掲げたロスタイムの表示は「10」。 10分間のロスタイム! 確かに度重なるラフプレーがあったとはいえ、10分は長すぎだろうとも思ったが、ピッチ上の選手たちよりも荒れに荒れて収拾のつかないベンチへのペナルティも含んだとすれば妥当とも思われた。それほどまでにエスパニョールは「切れて」いたのだ。 しかし、9人となり、同点とされてもなおエスパニョールは攻め続ける。シュートが外れ、パスを止められるたびにどん、どん、とベンチを蹴る音が響き、途中交代した選手が今にも審判に殴りかからんばかりの形相になってコーチに止められている。もうこの試合がどうなってしまうのか予想もつかなかった後半49分、エスパニョールDFの頭上を抜けるクロスがゴール前に上がる。そこにいたのはまたしてもマイク・ハーフナー。ヘディングでのハットトリックを決めるゴールが突き刺さり、そのままこの試合をものにしたのだった。 試合後もベンチを殴り、ボトルを蹴り、審判を罵り、怒りの収まらないエスパニョールのあまりにも生々しい、激高した感情の光景に、しばらく言葉も思いも出なかった。彼らは糸が切れた凧のようにふらふらと無軌道なのではなく、暴走する原子炉のように手がつけられない様子だった。どちらにしても「気持ちが切れた」ということには変わりはないのだけど、今まで見てきた「気持ちの切れ方」とは全く違うものだった。 僕が今までよく見てきたのは、試合のどこかで「もういいや」と消極的になってどんどん局面で負けていく選手たちであり、退場処分になったとしても諾々と引き上げる後ろ姿だった。けれどもエスパニョールの彼らはそれとは全く正反対で、何度ファウルをとられてもすぐに納得することはなく、審判に抗議し、それでも収まりのつかない棘だらけの気持ちが余計プレーに現れてしまう姿。 それを「気持ちが先立ってしまう若さ」と言ってしまえばそれまでだし、この試合で見せた彼らのプレーは間違いなく非難されるべきものだけれども、その奥では16歳そこそこにして「気持ちの強さ」を誰よりも強く持つということを知っていて、なおかつそれをきちんとプレーで表している姿が僕には驚きだった。 おそらくスペインだけでなく、フットボール的なヒエラルキーが高い国々においてはそんな「気持ちの強さ」というのはすでに教えるまでもない不文律というか国民性のようなものになっていて、その気持ちが刷り込まれているからこそあんなに強いのかもしれないな、と思ったりもした。そしてこれほどまでに(いい意味での)強い気持ちを持ち続けること、それを絶対に切らさないことというのは、勝った日本代表にも言えることであり、何度でも何度でもあきらめずにアタックを繰り返したからこその勝利でもあったわけで、この大会に参加した全てのチームが僕にそういう「気持ち」がどんどん伝わって溢れてくるような試合を見せてくれた。「メンタル」「タフネス」なんて格好つけた言葉じゃなくて、「勝ちたい」「負けたくない」というただひたすらにまっすぐな気持ち。その「気持ち」を再確認することができた4日間だった。 札幌はジョアン・カルロスが去り、張外龍新監督のもとで立て直しを余儀なくされた。しかも(そして「またも」でもある)崖っぷちでの立て直し。 けれど今チームが崖っぷちにいるとかそういうことはもう抜きにして、純粋に「勝ちたい」という気持ちを見せて欲しいというのが僕の希望であり、そんな勝ちたい気持ちがあるのなら結果にして見せてくれるのがプロであるとも思う。それはスコアだけでなく、試合の中身においても、プレーの一つ一つにおいても。 張監督は「気持ち」を何より重視する。勝ちたい気持ちを誰よりも強く持つこと、それを誰よりも強く見せること、そこからまず始めることが大事だと思う。そんな札幌だからこそ、僕は札幌が好きなのだ。 気持ち、見せてください。
posted by retreat |23:36 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月27日
CONSAISM clasics #44
clasics #44、なんか斜めに構えているっていうか何というか、な回。
J2のリーグ戦が半分終わった7月の初めから半ばの中断期間。J1ではここ数年よりはずっと面白い(少なくとも鹿島か磐田かの二択ではないので)優勝争いが繰り広げられていて、試合がBSで放送されているものであれば片っ端から観ていた。鹿島と磐田のいわゆる「2強」がそれぞれにどこか不安定な戦い振りを見せていることもこの混戦のひとつの要因だろうけど、オシム監督のもとに鍛えられた市原の試合がとにかく面白い。走って走って走って奪って奪って奪ってスペースに走る。村井が坂本が阿部がクロスをどんどんと上げてそれをまたチェ・ヨンスがばしばしと決めていく。一見したら体育会系なシンプルさだけど、そこに元から市原に見られた技術の高さが組み合わさってそれがまた相乗効果を産んで、どこか学者然として何をしでかすかわからないようなオシム監督の表情と相まって僕のフットボール的好奇心を膨らませる。ちなみにこの原稿を書いているのは磐田対市原戦の直後、チェ・ヨンスがヴァンズワムをあざ笑うかのようにふわっと浮かせたPKの余韻がまだありありと残っているぐらいの時間だ。タフで締まったいい試合だった、と思う。 さて、そうすると札幌の試合がなかったこの2週間ほど僕は何をしていたのかというと、相変わらず本を読んでばかりいた。なにしろ自分自身で憶えている最初の自分が「畳の上に寝転がって絵本を読む自分(当時2歳)」くらいなので、ほぼ生まれた頃からずっとなにかの文字を読むことに時間をかけてきて、例え財産が無くても本にかけるお金には糸目はつけないというのがもう自分の中でひとつのルールにされてしまっている。どうしても糸目どころか糸くずも見つからないときは父の書棚をひっくり返してよくわからないながらも何か文字を目で追い、それでもなければ新聞を隅から隅まで、それこそ株価の欄に至るまで読むような子供だった。今思い返すと嫌な子供だとつくづく思う。 どうしてそこまで本を読むこと(文字を読むこと)が好きだったのかというと、文字というひとつの定まったスタイルから拾い上げた情報だけを使って、そこにある情景や物語、あるいは100年も1000年も先の世界、そして今いるこの世界とは全く異なる別の世界を想像することができたからだった。知らない言葉は調べて覚えて、文章の使いまわしに感嘆したり難渋したりしながら読み進め、そこからしだいしだいに浮かび上がってくる世界やその世界を作り上げた作者の掌まで想像し、僕の頭の中に創造されていくのがとても好きだった。そうやって本を読み続けて20年以上、たまった知識は多いだろうけれどもほとんどは今テレビでやってるアレ、「トリビア」だったりもする。でもまあそれでも楽しいからいいんだけど。ちなみに僕はあんまりマンガは読まない。なぜかというとそこには言葉以外に「絵」というものがあるので、それが存在することによって僕自身の創造できる「世界」がどうしてもその絵に規定されてしまうからだ。それでも読むマンガがあったならば、それは僕がものすごく好きな絵を描く人であったり、マンガでしかできない表現があったりするからだったりする。しかしこうして本ばかり読んできたせいで、僕はその世界に結構引きずり込まれてしまってリアルの世界ではなかなか人付き合いが苦手だったりとっつきにくいやつだと思われているようで僕自身もそれを痛感している。とりあえず思ったことをきちんと相手の顔を見て伝えるということはとても大事だとしきりに思うこのごろ。 じゃあ自分はただの本オタクで引きこもりがちなヤツなのかと言われればまあ否定はできないのだけれども、本を読むということで国語の成績はよかったということ以外にとりあえず身に付いたのは「ものごとを読み取ろうとすること」だ。ある文章を読んでそこにある風景や心情や作者のほんとうに言いたいことを読み取ろうとその文章の中にある世界を類推し、理解しようとする。そのことをずっと意識していたおかげでリアルの世界においてもそういう力(というか癖、なのかも)がついた。文章でなくても、目の前の出来事でも人の発したひと言であってもそういうことをまず第一に考える。その物事が行われている背景には、必ずそうせざるを得ない「状況」や「理由」があると思うからだ。例えそれが「なんとなく」という理由であっても、言い換えてしまえば「本能」といってしまうこともできるし、そういう「本能」が生まれた要因というのは必ず存在すると思って今まで僕はそうやって物事を考えてきた。そしてフットボールもやっぱりそういう風に観るようになっていた。例えば左サイドのスペースに出された一本のパスにしたって、そこにスペースが生まれたのは中央なり右サイドなりで相手の注意をひきつける動きがあったからこそだし、そこにパスが出されたのは味方がそのスペースに動いていってパスを受けチャンスを作り出す動きを戦術的なものとして叩き込まれているから、はたまたさっきの「本能」的なものであれ予測されてのものであって(「苦しまぎれ」という理由もたまにある)、そこにボールが出てフィールドでどういう変化が起こるのか、つまりゴールを生み出すためにどうするべきなのかというのをプレイヤーも監督も考えているからこそのパス一本、トラップひとつなのであって、やはり僕が考えて行き着くところは「フットボールというのはかくも考えさせられるスポーツなのか」ということなのだ。そうして味方のことを考え、自分のことを考え、敵のことを考え、その結果行き着いたボールの流れを見てまた僕はそれぞれのことを考える。そのボールの行き着く先と、そのボールの交差によってフィールドに描き出される世界を。そうして絶対にどう考えてもだれに聞いても「わからない」という答えしかでないプレーやゴールを見ることがある。そこがまた僕の好奇心を刺激して、また深くフットボールにのめりこんでいく。答えの出ないミステリを読んでいるような、結果があって理由をどうしても導き出せない戯言だらけの推理小説のような、そんなところが面白いのだと思う。このフットボールというものはまだまだ僕なんかの想像力が及びもつかないところがいっぱいあるし、多分その量は増えこそすれ減らないだろう。どうやらこの「フットボール」という名の本はまだまだ読み終われそうにない。
posted by retreat |22:16 | classics | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年04月24日
CONSAISM clasics #43
clasics #43です。「夏と私とイバンチェビッチ」というタイトルとともに、個人的にはかなり好きな文章のひとつ。
JR札幌駅から大通公園へと続く道をそぞろ歩くのがなぜか好きで、晴れの日も雪の日もこの道を歩いている。札幌を離れてから、お盆や正月に帰省してきたときはまずこの道を大通公園までのんびりと歩いて札幌の空気を吸い込むのがひとつの儀礼のようになっていて、夏なら大通公園で青空に噴水の湧き上がる様に涼みながら往来をぼんやりと眺めるも良し、また冬なら冬で雪と寒風で冷えた身体を喫茶店で温かいカフェラテでも飲みながらこれまたぼんやりするも良し。そうしてこの癖は札幌に戻ってきた今も変わらずにいる。 この間も同じ道を歩いていた。そのときは札幌駅を背にして右側、道庁に近いほうの道を選んで歩いていて、札幌第一ホテルの脇を通り過ぎるときにはその1階に出店しているスターバックスが視界に入る。ちょうどガラス張りのカウンターの部分がちょっとだけ歩道にせり出していて、店の中からの視線は歩く僕らを回遊水槽の中の魚達でも眺めるかのよう感じてしまう。いつもならそんな光景には慣れたので歩いていってしまうのだが、一年前のある日に、僕はそこにある二人の人物の姿を認めて、立ち止まらずにはいられなかった。当時札幌の監督であったラドミロ・イバンチェビッチと、同じくコーチであったミオドュラグ・ボージョビッチだった。 柱谷哲二元監督の更迭によって札幌にやってきた、東欧のブラジルと呼ばれた、ユーゴスラビア(現セルビア・モンテネグロ)よりの救世主。僕はこの人の名前を寡聞にして知らず、戸惑いながらもその経歴とメディアの大きな報道を見て、とりあえず諸手を上げて歓迎してみた。そして二人を始めて見たのは6月の御殿場合宿のとき。グラウンドにはまずボージョビッチが姿を見せた。時を同じくして加入したFW、バーヤックとともにゆっくりとグラウンドの外周をランニングし始める。しきりに彼はバーヤックに話し掛けていて、それは初めて日本に来たまだ若い彼の緊張を早くほぐしてやろうという風に見えた。そして理知的で紳士的に見える彼の姿、でもその底には計り知れないフットボールへの静かな情熱があるだろうということも感じたような気がした。 全体練習が本格的に始まる頃、イバンチェビッチ新監督がやってきた。ジャージを着たその体躯はぱっとみたところ「フツーのオジサン」というような感じで、このひとが本当に札幌を変えるんだろうかといった第一印象だった。ハンチング帽に新聞と濃い目のコーヒーを添えてベオグラードの街角に置いたらそのまま風景に溶け込んでどこにいるのかもわからないような、「フツーのオジサン」的な風貌。まあ実際には僕はベオグラードには行った事は無いのだが。ともあれ、僕にとってそれがイバンチェビッチとボージョビッチとの最初の邂逅だった。 ワールドカップが終わり、Jリーグが再開に向かっていく中、札幌も力をつけているように思えた。選手のコメントからは充実感があったし、マスコミの記事もこの実直な新監督の指揮を好意的に捉えていた。そんな中で僕は、7月初めの1週間ほどを実家で過ごすことになった。自分の中のどこかで無理がたたったのか体調が悪化し、2週間の静養を医者から言い渡され、とりあえず半分を実家で過ごすことにしたのだ。まだ夏の盛りにはちょっと遠い午後の日に、いつものように僕は札幌駅から大通へとあてども無く歩いていた。風は爽やかだったけど、僕の心はこれからの焦りと不安と疲れで淀みっぱなしだった。その途中で、僕は二人の姿を見たのだ。そのスターバックスの、ガラス張りのカウンターの向こう側に。回遊水槽を眺められる向こう側から見たら、そんな僕の姿はさぞかし生きの悪い目の濁った魚に見えたに違いないだろう。でも二人はそんな僕や他に過ぎ行く人々には目もくれず、何かを話していた。白に緑のアクセントがついた紙コップを前に、イバンチェビッチが熱心に手ぶりを交えながら話している。ボージョビッチがそれを冷静に聞いている。その光景がしばらく続いていて、僕はそれを見過ごして歩くことが出来ずに二人を見つめていた。それのほんの数秒間だったのだろうが、なぜか僕はとても長い間彼らを見ていたような気がして、突然にそんなことをしていた自分が下卑た感じがしてなんだか恥ずかしくなって、ちょっとだけ早足でまた歩き出した。 あの時の彼らはとても、とても、熱を発しているように見えた。札幌をどうにか立て直していこうとしている、彼らはそれを成し遂げられると信じているのだ、と思った。こんなことを、あんな熱を、これほど身近に感じたのは初めてだった。 あの時二人は何を話していたのだろうとふと思う。戦術なのか、戦略なのか、それともそれすらを超えたフットボールの哲学とも言えるような話だろうか。あれからおよそ一年が経って、彼の思いが聞きたいと何故か僕は思っている。そうして僕はこう言いたいのだ、確かに結果は伴わなかったが、あなたが札幌で成したことは間違っていなかったと。少なくとも僕はそう信じているのだと。もう一度会う機会があったら、僕はそう言いたい。そして僕はあなたの姿に励まされたのだ、と彼に感謝したい。そんなことを思い出しながら、なんでもないのに勝手に一人で少し恥ずかしく思いながら、僕はあの時イバンチェビッチの座っていた場所で、揺れ動く回遊水槽を眺めている。今年は去年より暑い夏になって欲しい、その熱がずっと続いて欲しいと思いながら。
posted by retreat |22:37 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年04月21日
CONSAISM clasics #42
clasics #42です。札幌に帰ってきて思ったこと雑感、てな感じ。
リーグの開幕から約3ヶ月弱、よくもまあいろいろなことがあったものだと反芻する。 開幕でのまさかの敗戦から守備は崩壊攻撃は決定力不足を露呈、ジョアン・カルロスの外科手術(荒療治とも言う)で守備陣は安定してきたものの怪我による戦線離脱は重症軽症後を絶たず、頼みの綱の外国人はベットがいきなりブラジルに里帰り、とどめにご存知の通りウィルのアクシデント。これだけ短い期間でこれだけマイナス要因がぞろぞろと出てくるのは未だかつて無いんじゃないだろうかと思うくらい。それでも5月はどうにかこうにか無敗で乗り切っている。残念ながらそれも6月の早々に途切れてしまったけれども。 今年はJ2のリーグ戦以外にもいろいろなことが春の訪れとともに新しくスタートを切っていて、こっちは喜ばしくもプラス要因。ひとつは北海道U-18プリンスリーグ。道内で選ばれた8チームがリーグ戦を戦いながら、北海道の高校生世代のサッカーシーンの底上げを図るために発足された。そしてこのリーグに参戦しているひとつがコンサドーレ札幌ユース。2節を終了して、1勝1分けとまずまずのスタートを切っている。この時期に北海道の学校のサッカー部、あるいはクラブチームが集まってひとつの大きな試合を行うということは今までになかったはずで、どのチームも試合運びがうまくいかなかったり、連携が取れないことが多かったりする。戦術自体も守備から入るチームが多く、まだまだこれから、という感じがする。これが夏になり、初秋になり、クラブユース選手権や冬の高校選手権をだんだんと視界に大きく捕らえていくにつれて、どのチームもそれぞれのチームの色が出た成熟したプレーを見せてくれるだろう、と勝手に期待して思っている。 そしてもうひとつ新しく始まったのがサテライトリーグ。宮の沢でのホームの開幕戦には2300人を超えるファンが詰めかけ、そして東京V戦ではリーグ初勝利をものにした。宮の沢の雰囲気は厚別やドームでのトップリーグとはまた違うもので、あまり肩肘張らずに楽しもうという感じである。そんな雰囲気の中である選手はトップでの出場を狙いアピールし、ある選手はルーキーとしてプロの世界の当たりの強さや手ごわさを次第に身に付けより逞しくなろうとし、またある選手は怪我からの回復を確かめ、試合勘を取り戻しつつある。そしてサテライトリーグの参加の意義のひとつとして「若手育成」を掲げるこのチームにおいて、ユースからも将来を担うであろう幾人もの選手がすでにそのピッチに立っている。そんな光景を、多くのファンがスタンドで温かく見守り、声援を送っている。いいプレーには拍手を、悪いプレーには「次だ、次!」と励ます声が挙がる。それは厚別やドームとはまた違う、ある意味殺伐とした「戦い」よりも、未来の萌芽を育てていこうとする「成長」を楽しみにして見守っていこうという雰囲気。そして宮の沢はピッチが近く、「生」のサッカーを見ているんだなあ、という気がいつもよりする。こういう気持ちでサッカーを見るのも、普段のしのぎを削って削って削りまくるようなリーグ戦とは別の楽しさがある。トップと比べてサテライトは数試合しかないが、こういう雰囲気をこれからも楽しめるということはとても嬉しいことだ。 こうして今年のフットボールシーンは、僕の周りだけでも今までに無いくらいの変化を見せようとしている。いろんなことが始まって、広がって、それらが全てつながりながら新たなひとつのシーンを作り上げようとしている感覚を覚える。プリンスリーグやサテライトはそんなシーンのひとつだ。そして、そんなシーンがありとあらゆるところで始まり、それらがどこかでちょっとずつつながり形作って、日常に次第に溶け込んでいくもの、それがこのコラムのタイトルの一部でもあり、僕が言いたい「FOOTBALL」と「LIFE」っていうやつだと思っている。フットボールだけじゃなくてもひとりひとりのシーンがどこかでつながり、また別のシーンを作り出し、それが緩やかな連鎖とともに変わり続けていく。嫌な事だってあるけれど、全てが嫌なことばかりではないし、ある変化が起こって、それが僕達のシーンに、そして僕自身にどう作用して僕の内面や外見がどう変化していくのか、それを考えると心配事は多いけれどもそれほど悪い気もしない。「ライク・ア・ローリングストーン」、もしくは「生々流転」ってところか。 僕自身にも大きな変化があった。一言で言えば、アウェイからホームへ。変化を楽しむということを本当の意味で出来なかったのであろう僕はここに戻って一休みして、再出発をするつもりでいる。さながら渡り鳥のような気分。そうして僕にかかわるいろんな変化を感じて、それを楽しんでいける存在になりたいと、そう思っている。そうしてあの宮の沢の雰囲気のように肩肘張りすぎずに緩やかに穏やかに、しばらくは過ごしてみようかと思う。来るべき新たな変化をもっと楽しめるように。そうして僕は新たな「シーン」に触れたくて、またスタジアムへ足を向けたい、と思うのだ。
posted by retreat |23:34 | classics | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年04月18日
CONSAISM clasics #41
clasics #41です。ちょうど日韓ワールドカップから一年後の話。 ちょっと肩の力が良い具合に抜けてて、個人的に好きな回。
一年前の5月31日、夜あなたは何をしていましたか? 一日の仕事を終えて、帰り道についていましたか。それとも家にいましたか。まだ仕事中でしたか。誰かと一緒でしたか。それとも一人でしたか。日本と韓国で開催されたワールドカップの開幕戦、王者フランスと、未知の国だったセネガルとのゲームを、どこで見ていましたか? はて、と僕は思い出すまでにしばしの時間を必要とした。このところ一年前の記憶どころか昨日の夕食の献立さえも憶えていないような健忘症っぷりなのでちょっとしたことが思い出せずに苦労することがよくあるのだ。・・・ああ、思い出した。あの試合は新宿で見ていたんだった。大画面に映されるとってつけたような開会式のあと、「ラ・マルセイエーズ」の合唱とそこに重ねて大写しにされたジダンの顔を見て、ああワールドカップなんだと実感したんだっけ。後ろの席にはドイツ人らしい一団がいて注文するのに難儀していたっけ。よくわからない若者が騒いでいたっけ。ジャパニーズ・フーリガン!とか叫んで。それに僕は気分を悪くしたんだった。うざったいからつまみ出してくれ店員さんなんて思ったりしていたんだっけ。そしてキックオフ。リズムをつかめないフランスに対して、開幕の緊張などどこにもないように奔放に、でも意外に統制の取れた試合運びを見せるセネガル。次第に気づいていく、フランスはリズムに乗れていないのではない。疲弊していたのだ、最初から。セネガルのゴールに、店の中では落胆と驚きがないまぜになった歓声があがる。4年前の輝かしいフランスはどこへ行った?と疑問符を頭の中に並べながら見ているうちに、開幕戦はどんでん返しの幕を開けて終わった。今になってもうまく形容できないでいる熱気がくだを巻き、僕を戸惑わせ、狂わせたワールドカップの始まりは、そんなふうだった。 あの一ヶ月、僕はどうせ行けないだろうと思っていたワールドカップの試合を生で見ることが出来て、「si se puede!」が僕の中での流行語になって、新宿で「テーハンミングッ!」の大合唱を聴いて、日本対トルコ戦では当たり前のように代表のレプリカを着て会社の会議室で試合を見た。青いシャツとイングランドの7番のユニフォームが日本中を塗り分けた。わけのわからない焦燥と無軌道な高揚感が日本中を突き動かしていたように思えた一ヶ月は横浜の夜に終わりを迎えて、みんな何事もなかったかのように普通の毎日に戻っていった。その「戻り方」のあまりにもあっさりとした切り替わりに僕はまた困惑し、その後に再開されるJリーグの行く末にちょっとした不安を抱いたりした。そんな流れの中で、一年後の事なんかわかりもしなかった。それよりも札幌の一部残留が全てに優先していた、という事実もあったけれども。 そうして一年後、である。なんだかんだと言いながらもJリーグの観客動員数は増え、サッカーに興味のある人が増え、何人かの代表選手は海外移籍を果たした。そこに深みは感じられないながらも広く浅く、なだらかにフットボールはその地平を広げていった。本当はワールドカップがあった一年前、僕はきっと日本のフットボールシーンはもっと大きく変われるものだとばかり思っていた。Jリーグはもっと盛り上がり、代表はもっと強くなり、もっとフットボールが楽しくなるとものすごくポジティブに考えていた。でも今になって、それは現実になったかというとそうではない。むしろ僕の浅はかさを助長して、自己嫌悪をちょっとばかり、いやかなり悪化させただけだった。まあ自分の考えが相当に甘かったってことなんだろう。そうそう自分の思うようになんか行かないし、総体としての世界は急激に変化することなどないのだろう。それがわかっただけでもオッケー、と思うことにする。 けれども僕はこれからもフットボールの世界において、こんなふうにポジティブに考え続けることをやめないだろうと確信犯的に思っている。いろんな街に大小問わずクラブが出来て、熱心に試合を見つめるファンがいて、フットボールが広がっていく。そんな妄想とも空想とも取られても仕方の無いような思いを、僕は止めることが出来ないし、止めるつもりも無い。それほどまでに僕はフットボールに憑り付かれてしまった人間になってしまったのだ。ボールはゴールに向かって前に進んでいく。なぜなら、それがフットボールだからだ。そして僕の人生も否応無しに前に進んでいく。なぜなら、それが僕の人生だからだ。そうして僕はゴールを奪われながらもゴールを決めるべく前に進む。取ったり取られたりしながらゲームは終わることなく続いていく。それが僕のゲーム。僕のフットボール。一年前も一年後も、今までもこれからも変わらない「前に進む」というポジティブな事実。それを僕はやっと実感しつつある。 この文章を書いている今日、札幌の天気はスガシカオの歌じゃないけれども宇宙まで突きぬけそうな青空で、僕が宮城スタジアムで「ワールドカップ」を体感したときもこんな汗ばむくらいの天気だった。メキシコ人もエクアドル人も日本人も、あの時あの場所にいたみんなが青空の下にいた。そして僕がこんなことを書かなくったって、青空はもの言わず続いていたのだ、ずっと。
posted by retreat |21:46 | classics | コメント(0) | トラックバック(0)