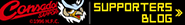2008年01月31日
毒入りギョーザと自己防衛
中国製冷凍ギョーザに殺虫剤が混入していて、千葉、兵庫両県で昨年12月以降、このギョーザを食べた計10人が吐き気や下痢などの中毒症状を訴え、千葉県市川市の5歳の女児が一時、意識不明の重体になった事件が広がりをみせていますね。 怖いですね。また中国ですよ。中国は、これまでも有害物質が混入した食品などを世界に向けて輸出し、人命に関わる問題をたびたび引き起こしているのに、安全に関する世界の常識からかけ離れた国民意識は一向に改善されていないようです。これで本当にオリンピックを開催できるのでしょうかね? と、いささか心配になってしまいます。 ところで、この問題を伝えるメディアは、行政の対応が遅い、という、いつもの正義面した論調で、最初の中毒患者が出たとき問題の食品を公表し、回収していれば被害が広がることはなかった、と因果関係が明らかになった今なら小学生でも言えることを主張していますが、だけど、それって、現実的には極めて難しいことだったと思いますよ。 12月28日に千葉市の二人が症状を訴えたのが発端のようですが、仮にですよ、仮に二人を診察した医師が神の啓示を受けたがごとく、この症状は殺虫剤が原因だ、殺虫剤はギョーザに混入していた、と断定して、保健所なり警察なりに通報したとしても、通報を受けた行政機関は、それをそのまま真に受けて、さらに加えて独断で、殺虫剤の混入は中国の製造工場だ、この工場製の他の製品にも混入しているおそれがある、と断定して、その事実? を公表して市場からの商品回収を命ずる、なんてことは、現実的には出来ないと思いますよ。もし、そういう措置を取って、それが間違いだと分かったときは、莫大な損害賠償問題になりかねませんからね。 ギョーザを食べて急性中毒症状を起こしたと訴えがあった場合、それが集団食中毒のような大きな広がりを見せている場合は別として、今回のように特定の地域の少数の者(今回の事件も最初は家族二人)であったとき最初に疑うのは、そのギョーザが腐敗していたのではないか、という個別事情で、食品検査の結果、ギョーザに殺虫剤が混入されていたことが明らかになった段階でも、これまでスーパーの陳列商品に毒物や異物が混入される事件が起きているので、今回のケースも何者かが殺虫剤を混入したのではないか、という事件性を疑うのが普通の対応でしょう。 行政の対応が遅い、という論調の報道が多いですけど、現場における、あらゆる可能性を考慮した検査や調査を考えると、一ヶ月あまりで結論を出した今回のケースは、そこそこ早い対応だったと思いますけどね。 行政の対応が問題だとか、検査態勢の不備だとかの問題も確かにあるとは思いますが、そんなことより問題の根っこは、共産党一党独裁の国、中国ですよ。 昔、中国の高官が、社会主義体制のまま「豊かになれる人民から順に豊かになろう」というスローガンの下に自由経済を導入し、今では、世界経済に影響を与えるほどの大国になったというのに、中国国内の人民の意識は、儲かれば何でもあり、というふうに歪んだ方向に進んでしまったのではないのでしょうかね。 困ったもんだ、と手をこまねいていても問題の解決にはなりません。こうなったら自己防衛です。個人的には、値段に引かれて中国製品に安易に手を出すことをやめ(これまでは、安さに惹かれて手を出していた)、たびたび問題を起こす中国という国を信用しないことによって自己防衛を図るしかない。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:11 | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年01月30日
ほっかいどう語3「なげる」
1月28日の「しまふく寮通信」の文書の中に、こんなのがありました。 『結局、怖い話を聞きすぎたゴミ投げ当番は、「怖いので明日投げてもいいですか・・?」』ユースの高校生の発言です。 それでを読んで思い出しました。昔、群馬出身の自衛官の友人から聞いた話を。 本人の体験談だったのか、見聞として聞かされたのかは忘れましたが、北海道の駐屯地に着任した新人自衛官が上官から「このゴミ、なげてこい」と命令され、「え? 投げるのですか?」と確認したら「そうだ、なげるんだ」と念押しされたので、これも訓練の一環かと思って、ゴミを力一杯遠くへ投げたら、怒られた、という話です。 道民なら誰でも知っているとおり、北海道における「ゴミをなげる」は「ゴミを捨てる」の意味ですが、全国共通的な似たような表現に「仕事をなげる」という言い方があります。このときの「なげる」は、放棄する、という意味がありますから、ゴミを捨てることを「なげる」と言っても、あながち間違いではないのかな、という気がしますけどね。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:00 | コメント(3) | トラックバック(1)
2008年01月29日
重ねゆく歳とともに思うこと
北海道新聞に北広島市西の里地区生涯学習振興会主催の講演会で曽田選手が話した概要が載っていました。 小学4年生で地元のサッカー少年団に入ってからのサッカー人生において常に夢を追い続けてきたことを紹介し、「いくつになっても、夢を見ることは大事だし楽しい」という話しをしたそうです。現在の夢は、日本代表に選ばれることだ、とも語っています。 平凡な人生を歩む人にも、プロサッカー選手の人生を歩む人にも、皆それぞれ同じように時は流れます。 「やりたいこと」は何かを模索しているうちは若いのです。 やがて「やり残したこと」は何かを探すようになります。 だけど「やり残したこと」に気付いたら、それが「やりたいこと」に変わります。 そして、少しだけ元気になります。 そんなことを繰り返して、人は歳を重ねていくのです。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:27 | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年01月28日
流氷が接岸しなかった年
季節ネタをひとつ。 先日、オホーツク沿岸の網走に流氷が接岸したと報じられました。 流氷はアムール川から海に流れ込んだ水が凍り、それが南下してオホーツク沿岸に至り、勢いのあるときは知床岬を回り込んで、時には釧路にまで流れ着くことがあります。 その流氷が近年、地球温暖化の影響なのか、密度と勢いが弱くなってきています。かって、びっちり接岸した流氷の上を歩いて知床半島を一周した某大学探検部もあったというのに、今では氷がユルユルで、そんなことは無理です。 この流氷が網走沿岸に一度も接岸しなかった冬が一度だけありました。 確か昭和40年代後半から50年代前半の、ある年だったと記憶しています。オホーツク海は冬になると流氷に埋め尽くされ、白い雪原と化すのが通常の風景と思い込んでいたので、冬に青黒い水面を見せている海を奇異に感じたものでした。 そこで、おじさん(当時は、おじさんではなかった)達が何を考えたかというと、これは、魚たちが、どうしているのか確認できる絶好のチャンスではないか、ということです。通常の冬の場合、オホーツク海は流氷で被われるので、その下に生息している魚たちが、どのようにしているのか有史以来だれも確かめた人がいなかったのですから。 おじさん(しつこいですが、当時は、おじさんではなかった)達は、釣竿を肩に担いで、沖に向かって突き出している防波堤をワッセワッセと歩いて行きました。 ここいらへんで、いいんでないかい? カレイのポイントです。おじさん達は、投げ釣りセットを準備し、エサ(イカだったような気がする)を付けて、流氷のない海に投入しました。 待つこと2時間。 竿先はピクリともしません。流氷がないといっても厳寒のオホーツク海です。体が寒さで硬直してきました。 魚、どうなってんねん? 食い付かへんな、いないんとちゃうか? ほな、魚、どこ行ったん? 知りまへんがな 2時間後、肩を落として防波堤をトボトボ戻ってくるとき、一陣の寒風が背中を押しました。遠くからSLの走行音が聞こえてきます。いつの間にか陽が傾いていました。 おじさん達の結論は、冬のオホーツク海の魚はエサに食い付かない、ということでした。 ね? バカでしょ? と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:22 | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年01月27日
MFの内なる戦い
いよいよ第一次キャンプが始動し、チーム内におけるレギュラー争いが始まりました。 J1に昇格しても、まず堅守ありき、というチーム戦略は変わらないと思いますが、J1はJ2より攻めてくるチームが多いので、ボランチには守備力が売りの選手が有利になり、両サイドは、攻撃力のある選手が有利になるのかもしれません。 MFの新入団選手は、パルメイラス(ブラジル)から柏にレンタル移籍していたアルセウ選手、新潟からレンタル移籍のディビッドソン選手の2人ですが、この両選手は守備力とボールを奪った後の展開力に定評のある選手ですので、この2選手がレギュラー争いで先行していると想定して、残りの選手は一層頑張らなくてはなりません。 MFの選手たちは、ベテランと若手のバランスがとれていますが、若手の中には昨季、力を付けて頭角を現し、今年を勝負の年と考えている選手もいます。 レギュラー候補はキャンプの中で選別されることになると思いますが、MFの登録選手は13人の大所帯で競争の厳しいポジションです。 特にベテラン各選手は、グァムの空の下で必死に汗をかいて自身の能力を再アピールしないと、今季は出場の機会を失う可能性もあります。練習後の息抜きでビールなどを飲み過ぎないようにしてください。 キャンプの成果に注目しています。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:12 | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年01月26日
北海道知事へ
北海道は、出資した資本金の8割減資に難色を示し、融資金に関しては返済計画を明確にすることを求め、補助金に関しては来年度から打ち切ることを決め、HFCに対しては、経営責任を明らかにするよう求めたそうです。道の根底にある考えは、これらのお金は「税金」だから、ということのようです。 この問題を考えてみたいと思います。しかし、「出資金」と「融資金」と「補助金」は、それぞれ性格が異なるお金なので、分けて考える必要があります。
posted by masa2007 |18:53 | コメント(3) | トラックバック(0)
2008年01月25日
オオカミを野に放つ
サッカー関係のネタが続かないので、ちょっと脇道にそれた話しを。 ちょっと前の北海道新聞に「道路沿いの雪崩はシカの群れも引き金になっている」という記事が載っていました。それもトップで。 一週間ほど前の道新夕刊に「オオカミに熱視線 生態系修復へ期待」という記事が載っていました。増えすぎたエジシカに関する記事です。 今冬は知床岬でエジシカを試行的に駆除しました。エジシカが、あまりにも増えすぎたので一部を試験的に駆除(銃殺)したようです。自然を守るため、これも自然の存在であるはずの野生生物を人為的に駆除するという矛盾です。しかし、それほどエゾシカが増え続けているということなのでしょう。 知床は世界自然遺産に登録されましたが、世界自然遺産というのは、簡単に言うと、現在の自然が世界的に貴重だから、原則としてそのまま保存しましょう、ということです。 しかし、知床における生態系が崩れた現状では、エゾシカの増殖が他の植生などの生態系を破壊することは目に見えているし、現にそうなりつつあります。 かっての蝦夷地には、エゾオオカミが生息していて生態系が確立されていたのですが、和人が入植して家畜を襲うオオカミを駆除してから、このバランスが崩れました。 そこで一部の人たちが、北方圏に棲息する野生のオオカミを北海道に放ち、かっての生態系を復活させるべきだ、と主張しています。 この話を聞いたとき、北海道最後の一匹と言われているエゾオオカミの剥製を見たときの衝撃を思い出しました。見たのは剥製ですけど、そのとき、あまりの迫力に後ずさりしてしまいました。イヤだよ、あんな恐ろしい動物と山の中で遭遇するのは。これが素直な感想でした。 しかし、よく話を聞いてみると、かっての蝦夷地で人間がオオカミに襲われた事故は一件も起きていないそうです。それどころか、世界的にみてもオオカミが人間を積極的に襲った事例はないそうです。(真偽のほどは不明) 最近、考え方が変わってきました。 斜里町宇登呂や羅臼町における、人間を恐れなくなって傍若に振る舞うエジシカを見るにつけ、地球温暖化の進行で、これから冬の自然の厳しさで自然淘汰される頭数が少なくなる状況を思うにつけ、オオカミが棲息していた時代のバランスのとれた生態系に戻した方が、世界自然遺産である知床の本来の姿になるのかもしれないな、と。 数日すると心が揺れます。 人為的にオオカミを放った場合、エジシカというエサに恵まれたオオカミが増えすぎて、オオカミの群が北海道全域に拡散したらどうなるのだろう? 大雪山で夜、オオカミの遠吠えを聞く? 考えただけでゾッとします。そのときは、100年前のようにオオカミを人為的に駆逐するのだろうか? 今のところ、賛成、反対の心が行ったり来たりしています。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:23 | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年01月24日
DFの内なる戦い
いよいよ第一次キャンプが始動し、チーム内におけるレギュラー争いが始まりました。 J1に昇格しても、まず堅守ありき、というチーム戦略は変わらないと思いますが、J1はJ2より攻めてくるチームが多いので、J2のときのように、ちょっと引き気味に守る守備では、ほとんどの時間、攻められ続けるという試合になる可能性があるので、今季は少しゾーンを押し上げて、これまでより一層強固な堅守を目指す戦略を考えていると思われます。だからこそ、補強がDFから始まったのでしょう。 そのようなチーム戦略の中でDFのレギュラーが争われます。 DFの新入団選手は、柏レイソルU-18から新加入の堀田選手、浜松大学から新加入の柴田選手、清水エスパルスからレンタル移籍の平岡選手、ヴィッセル神戸からレンタル移籍の坪内選手、サンフレッチェ広島から移籍の吉弘選手です。 この内、各世代の日本代表に選出された実績がある坪内選手や、サンフレッチェ広島から移籍してきた吉弘選手の2選手に期待が集まっているようです。西澤、曽田、池内、西嶋の各選手は、この二人がレギュラー争いで先行していると想定して、グァムの空の下で必死に汗をかいて自身の能力をアピールしないと、ちょっとヤバいことになるかもしれません。 キャンプの成果に注目しています。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:21 | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年01月23日
集合写真が消えた
「コンサドーレ札幌公式モバイルサイト」を開くと、コンサドーレの直近の出来事の写真が目に飛び込んできます。つい先日までは、昨季最終戦で劇的な勝利をおさめ、J1昇格とJ2優勝を決めて札幌ドームで喜ぶメンバーの写真でした。ど真ん中で曽田選手が大股を開き、左端で社長と監督が肩を組んで笑っている写真です。 いつまでも喜んでいる状況ではない、ということだと思いますが、数日前から「J1を舞台に戦う赤黒の戦士たち!」というコメント付きで、三浦監督を中心とした今季メンバーの集合写真に変わりました。当然です。いつまでも浮かれている状況ではありません。厳しいJ1での戦いが待っているのですから。 その集合写真を見て、う? と思いました。これで全員か? 今日のブログは、その集合写真に写っている選手をチェックして、○○選手と○○選手がいませんよ、という書き込みをしようと思って、改めてサイトを開いてみたら… 「J1を舞台に戦う赤黒の戦士たち!」というコメント付きの写真が、J1昇格とJ2優勝を決めて札幌ドームで喜ぶ過去の写真に戻っていました。 ????? 何があったのですか? と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:21 | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年01月22日
GKの内なる戦い
いよいよ第一次キャンプが始動し、チーム内におけるレギュラー争いが始まりました。 GKのレギュラー争いですが、現時点において最も正GKに近いのは、レンタル移籍した06年の草津と07年のコンサドーレの2シーズンほぼフル出場して実戦経験が豊富で、チームの中で一定の評価を受けている高木選手だと思いますが、昨年12月に手術したヘルニアの状態が問題でしょう。その治癒具合の一つの判断材料は、キャンプイン当初から他の選手と同じメニューをこなせるか、別メニューになるか、だと思います。 高木選手が別メニューなったら、ちょっと不謹慎な言い方になりますが、他の選手にとってはビックチャンスです。 高木選手のヘルニアが完治していた場合でも、GKは二番手に付けることが非常に大事です。高木選手がJ1でも大活躍したら、今季シーズンオフに大宮から「帰ってこい」と呼び戻されるかもしれないし、二番手のGKという立場はJ2の3位のチームと同じで、正GKとの入替戦の権利保持者なのですから。 普通に考えれば二番手GKは、06年シーズン終盤から出場機会を得て、天皇杯では4回戦からレギュラー出場した経験がある佐藤選手でしょうが、06年天皇杯新潟戦で不用意にボールを置いて同点ゴールを奪われたり、今年の天皇杯TDK戦のPK戦で、お前なに考えてんねん? というキックを蹴ったり、セットプレーのとき無闇に飛び出す判断ミスや経験不足からピンチを招くことが多いので、監督・コーチの評価がどうなのかは、よく分かりません。 横浜F・マリノスから完全移籍してモチベーションが上がっている富永選手や、至近距離の反応の良さに定評がある高原選手も横一線と言えるでしょう。キャンプでしっかり自己アピールしてください。 キャンプの成果に注目しています。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:45 | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年01月21日
【○○くんみたいに
新加入選手の記者会見で札幌ユースから上がった横野選手が自己紹介で「~(略)~ ユースの先輩である石井くんや大伍くん、征也くんみたいにチームで活躍して中心選手となれるように努力したいと思います。~(略)~」と述べた、という内容を J's GOALで見ましたけど、この発言、本当なんですか? これを見たとき(読んだとき)正直、かなりビックリしました。ビックリと言うか、驚愕に近い驚きでした。 おじさん達の世代の人間にとって、先輩、それも同じ運動選手の先輩を、くん付けで呼ぶなどあり得ないことでした。そんな呼び方をしたら、まあ、人目に付かない部室に呼び出されて、かなり厳しい制裁を加えられても仕方ないくらい先輩に対して非礼なことです。 横野選手が記者会見という公式の場で、そう発言したのだとしたら、彼は普段から彼らをそう呼んでいて、いつもの呼び方が出た、ということになんでしょうが、今の運動部の先輩後輩の関係って、そんなふうに変わっちゃたんですか? それともサッカー界独特の風習なんですか? 横野選手だけが特異なんですか? うちの会社では新入社員が、たとえ同じ学校出身だとしても先輩を、くん付けで呼ぶことなんて、あり得ないことですけど… それとも今の社会では先輩でも、くん付けで呼ぶことが普通なんですか? そんなふうに変わっちゃったんですか? もしそうなら、おじさんは、完璧に旧人類化しています。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:08 | コメント(7) | トラックバック(1)
2008年01月20日
強くなるために
21日にグァムに入り、いよいよシーズンに向けてキャンプが始まります。 聞くところによると例年にも増して練習試合が多くなるとか。新入団選手の技量を見極め、既存の選手との相性をチェックするのでしょう。ああ、いよいよだな、という感じです。 あらゆる団体スポーツがそうだと思いますが、チーム同士が対戦するスポーツにおいては、戦略と戦術の二つの柱が重要だと思います。 戦略というのは、ゲームに勝つための総合的な駆け引きであって、具体的には、相手チームの長所を消し、自チームの長所を効果的に機能させる手段といえます。 シーズンを通して、相手チームの特質に応じた多様な戦略に対応できるチームをつくることは、監督の日頃のチームづくりの指導における手腕にかかっていると言えるでしょう。 一方、戦術というのは、個々のゲームにおける場面場面で、チームの総合力をいかに組織的に機能させていくかということです。 戦術は、個人戦術とチーム戦術に大別されますが、チーム戦術が機能する前提となるのは個人の技術です。確実な個人技術なくして総合的なチーム戦術のスキルアップはあり得ません。 チームとして強くなるためには、個人技術の向上と確立がまずあって、次に、その確立した個人技術を組み合わせた戦術があって、そして、相手チームに対応した戦略があるのだと思います。 コンサドーレの現在のメンバーで、どの組み合わせが最強か? まあ、そのことは、監督以下のスタッフが判断することで、おじさんたち部外者がとやかく言うことではないと思いますが、今季からは新たな戦いの場、J1のステージにおける強豪との戦いが始まります。 個人技術を向上させ、チームとしての戦術を練り、確実な戦略をもったチームになって(J2に戻らないよう)J1ステージでも勝ち進めるチームに仕上げてください。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:29 | コメント(0) | トラックバック(1)
2008年01月19日
アホな考え「ゴールの枠」
今日、スカパーで新ユニフォームを見ちゃったんですが… まあ、それはそれとして、シーズンオフの間、常日頃考えているアホなことを書いてみようと思います。 サッカーの試合で、もどかしいことの一つに、なかなか点が入らない、という厳然たる事実がありますね。日本だけではなく、世界中のサッカーがそうです。 バスケットみたいに点が入りすぎるのもなんですが、点が入りそうで入らないゲームにイライラすることも少なくありません。 シュートを打っても打っても連続してポストやクロスバーに嫌われる、なんてことが試合ではよく起きます。ポストやクロスバーの幅は12センチ以内と決められているので、狙ってもなかなか当たらないと思うのですが、現実にはよく当たります。不思議です。 そこがサッカーの醍醐味よ。 まあ、そういう見方もあるのかも知れませんが、もう少し点の取り合いというシーソーゲームも観てみたい気がします。 野球は9対8の試合が一番面白いと言われますが、サッカーも5対4ぐらいの試合を観てみたい気がします。 そこで、アホなおじさんの頭にアホな考えが浮かんできます。 既存のゴール枠(高さ2.44m×幅7.32m)の1メートル外側に、もう一つの枠をつくってゴールを二重枠にするのです。で、従来の内側の枠に入ったら得点は2点で、外側の枠に入ったら1点とするのです。 そうしたら、今よりエキサイティングなゲームになると思うのですが。 真剣に受け止めないでください。言ってるこっちだってアホになって、ほんの遊び心で言ってみただけですから。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:41 | コメント(1) | トラックバック(1)
2008年01月18日
公的支援の行方に関する私的見方
今日の読売新聞に「北海道は、コンサドーレ札幌を運営する「北海道フットボールクラブ」に対し、経営陣の責任明確化などを求める文書を提出、18日にも道幹部と児玉芳明社長が面談し、道側は改めて責任明確化など融資継続の条件整備を求める」という記事が載っていました。 道だって知っていると思います。 1994年当時、Jリーグプロチーム誘致のため「30万人署名運動」が行われたとき、最終的に31万人を超える署名が集まったことを。 当時、北海道初のプロチームであるJリーグを発足させるため、行政・企業・市民が三位一体となって運動を推し進めたことを。 道内若手経済人たちの奔走によって道内企業から出資が寄せられ、悲願の(株)北海道フットボールクラブが設立されたことを。その設立を道としても、地域活性化と地域への経済効果のため歓迎したことを。 経営陣の責任明確化を求める道だって知っているはずです。 累積赤字がふくらんだのは、早期にJ1に上がることを優先するため外国人選手中心の補強を行い、その人件費の負担が大きかったことが原因であることを。当時、その方針に道として異を唱えなかったことを。 その後、チームとしての成績が安定しなかったため入場料・広告収入が安定せず、赤字を積み重ねていったことを。 プロ野球チームと違い、地域密着型を指向するサッカーチームの場合は、特定の親会社からの支援がないことから、経営的に黒字にすることが極めて難しいことを。あの浦和レッズだって経営が安定するまでは、大企業グループの支援を受けていたことを。 経営陣の責任明確化を求めているけど、誰がどうやっても、親企業の支援のない道民・市民が支えるプロチームの場合、発足当初は赤字が避けられないことを。 そのような経緯や現状を知っていても、それでも、厳しい財政状況にある道の立場としては、資本金の8割減資によって1億2千万円の税金が消滅する事実を納税者である道民に説明して納得してもらう必要があるので、HFCに対しては、新聞記事にあるような対応にならざるを得ないのでしょう。 この新聞記事は、うがった見方をすると、道としては財政的に非常に厳しい立場にいるので、そのような立場の道の窮状を察して、HFCが道民の納得のいく回答を出してくれれば、道としては一種のアリバイを得ることができて継続的な支援の名目が立つので、だから、HFCさん、お願い、しっかりした回答をお願いしますね、という高橋知事からのメッセージではないのかな。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |20:11 | コメント(2) | トラックバック(0)
2008年01月17日
サッカーチームの企業体質
欧米企業(専門的能力を必要とする業種)では、社員を育てるという感覚が薄く(まったく、しないわけではないと思いますが)、最初から必要な能力を持っている人を採用する傾向にあるそうです。また、社員が他社から望まれて転出する引き抜きも頻繁にあり、そのような社員はキャリアアップが図られるので喜んで転出するようです。逆に能力のない社員は簡単にリストラされます。(以上、聞いたはなし) 一方、日本企業の場合は、専門的能力を必要とする業種であっても、新人を育てていくという感覚が強くあります。また、能力のない社員も含めた組織全体で業績を上げるという体質があり、それが日本独特の終身雇用や社員の会社帰属意識の高さになっているのだと思います。欧米とは人材に対する意識が根本的に違うのでしょうね。 という前振りをして、プロサッカーチームを考えてみます。 サッカー選手の移籍に関しては、外部から見ていると、選手は自分を高く買ってくれるところが一番と考えているようで、日本企業の体質に馴染んだ人間から見ると、チームに対する愛着心が希薄なように感じます。 選手にとっては、サッカー界が一つの会社であって、(株)サッカー会社の第一営業課に所属しているという意識よりも、所属はあくまでも(株)サッカー会社であって、移籍は、同じ会社内の第一営業課から第二営業課に異動する程度の感覚なのかもしれません。なんとなく欧米型企業の社員という感じがします。 プロ野球の場合は、チームの選手に対する保有権が強くて、たとえ選手が希望しても自由な移籍をなかなか認めませんし、選手個人もチームへの愛着というか帰属意識が強いような気がします。望まれた移籍であってもトレードとなると、多くの選手が嫌々ながら応じる、という対応を見せます。なんとなく日本型企業の社員という感じがします。 こうやってみると、サッカーチームの体質は欧米企業型といえるのかもしれません。 その対極にある日本生まれのプロスポーツである相撲(純粋なスポーツとは思っていませんが)の場合は、部屋をチームに見立ててみると、これは思いっ切り古典的な、それも丁稚奉公時代の日本企業(商店)の体質にみえます。だから、本質的に持っている気質が欧米企業型の外国人力士が時々問題を起こすのでしょうね。 と、おじさんは、思うわけです。
posted by masa2007 |19:37 | コメント(0) | トラックバック(1)